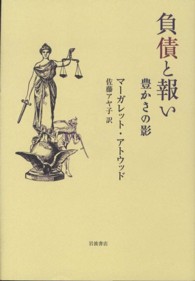出版社内容情報
およそ1500の島々から成る社会主義国家・キューバ。政治的にも経済的にも大国に支配された国家の、宿命からの脱出と、その独特な文化を見据えた紀行文学の傑作。(解説・佐高 信)
内容説明
「祖国か、死か、われらは勝つ」至るところで見受けられるこの標語には、キューバ革命の切実さがこめられていた。独特の人種構造と砂糖生産に限定された経済構造。それがつくりだしたキューバの人々の気質。政治的にも経済的にも大国の影響下にあった国家の、宿命からの脱出の歴史に、20世紀後半の最大の特徴を見る。国家と国家の支配関係における本質的な問題を見据えた紀行文学の最高峰。
目次
1 苦い砂糖
2 植民地の宿命からの脱出
3 キューバの内側から
4 シエラマエストラ山にて
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
13
革命冷めやらない1965年のキューバを訪ねた旅行記。『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス』でスペイン人によってインディオが虐殺されアフリカから黒人を連れてこられたことが語られていたけど、そして革命と共に富裕層がアメリカに逃げたということで、だから残ったのは貧しいキューバ人で社会主義革命のヴィジョンがあったというよりは、支配していた資本家や技術者がいなくなったので社会主義にするしかなかったようだ。2018/08/03
岡本匠
11
堀田善衛は若い頃によく読んだ。随分久しぶり。この本は元々岩波新書の本を文庫化したもの。革命の後、筆者がキューバを訪れ、考えた事を記したもの。フィデル・カストロの演説文が多く引用されるなど、キューバ寄りではあるけれど、当時には、キューバに対する比較的に正確な情報を伝えていたのではないか。 表紙は柄澤齊のデザイン、少し気になった。2017/06/25
波 環
9
1965年のキューバの6週間の旅の記録。堀田善衛は35年前、私が初めての海外旅行、スペインに行くときに恩師に言われて『ゴヤ』を読んだ。昨年、私はまたフランス、スペイン90日の旅をした。堀田が住んでいたスペインの村も通った。スペインでゲバラの肖像写真を掲げるレストランがあって、キューバ革命の本は読んでなかったから帰国して手当たり次第、関連本をよんだ。最後に来たのがこの堀田の本である。堀田→スペイン→ゲバラ→キューバ→堀田。どこまでも堀田善衛。1965年はキューバ革命が次段階になりゲバラがキューバから去った年2024/10/08
pyonko
7
キューバ危機から数年後の紀行。国名を聞いて思い浮かぶものは、キューバ危機、カストロ、チェ・ゲバラ位である。日本とは縁遠い国のイメージだったが、すでにこの時期から技術協力などが進んでいたことに驚きを感じる。極めつけは紡績工場の名前に浅沼稲次郎の名がついていることだろう。2009年時点ではまだ稼働していたらしい。小国故の悩み。特に共産主義にはNOを突き付けつつも、結果として旧ソ連に近づいていかなければなかったという経緯は興味深い。2014/07/24
sagatak
3
1964年の古い本だが、現代まで通用する内容だ。解説が1995年でソ連崩壊後に書かれたもので、キューバはさらにその後一波乱あったというのに、そのまま今でも通用する。現在まで一貫した国としての態度は変わらない。キューバに少しでも興味あるかたは必一読。2010/06/21
-

- 文具・雑貨・特選品
- ジュエリー絵画(R) サンリオ 花オト…