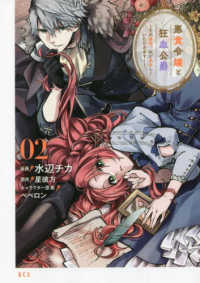出版社内容情報
小泉 武夫[コイズミ タケオ]
著・文・その他
内容説明
縄文時代のデンプン酒に始まり、豊穣祈念で神に捧げた弥生時代。平安時代から熱燗を嗜み、戦国の世では酒で契りを交わし、江戸時代には新酒わ求めて番船競争まで繰り広げる―。古来、日本人が深く愛し、育ててきた日本酒と周辺文化を、時代ごとの「味」とともに細微に検証。造り酒屋に生まれた発酵学の第一人者だからこそ書けた、日本酒大全!
目次
第1章 日本の酒の誕生
第2章 神の酒から人の酒へ
第3章 日本酒の成長と成熟
第4章 酒と社交と人生儀礼
第5章 酒商売ことはじめ
第6章 酒を競う
第7章 日本酒と器
第8章 日本酒、その嗜好の周辺
著者等紹介
小泉武夫[コイズミタケオ]
1943年、福島県の酒造家に生まれる。東京農業大学農学部醸造学科卒業。醸造学、発酵学専攻。農学博士。東京農業大学教授、国立民族学博物館共同研究員、(財)日本発酵機構余呉研究所所長などを経て、東京農業大学名誉教授。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なっぱaaua
44
小泉武夫先生の日本酒の歴史と文化をご教授頂ける本です。日本酒ってコウジカビであるAspergillus oryzaeのおかげですよね。この本は1992年に刊行されていますが、歴史と文化なら2021年に再発刊されても古さは感じませんね。まぁお酒がきっかけで戦いになったりするのはもう仕方のないことかもしれません。神々の話、酒屋の歴史、酒と儀礼、商売・競争・器、日本酒に関わることが小泉先生の解説を通じて面白く語られています。日本酒は料理との相性も含めていっぱい拡がりがありますね。~続く~2022/06/10
Shoji
33
日本酒の歴史と文化を語った本です。発酵学や醸造学を専門にしている先生らしい切り口で解説していますが、難しいことは書かれていません。民俗学的アプローチで日本酒を解説しており、とても興味をもって読むことができました。2023/04/12
うえぽん
21
造り酒屋に生まれ発酵学の第一人者となった筆者が日本酒の歴史、製法、文化を熱く語った作品。麹製法の普及前は、アジア一帯に見られる唾液のアミラーゼを用いた口噛み酒が造られ、近年まで祭事に用いられていたとは初耳。江戸の人々が今の3倍も酒飲みだったこと、灘伊丹等からの下り酒を届ける廻船間の激しい競争の様子、造り酒屋が「居酒致し候」という看板を掲げたのが居酒屋の起源であること、酒合戦の歴代記録が一斗八升というとんでもない量であることなど、酒の肴になりそうなエピソードが満載。伝統に倣った「主人設」を挙行してみたい。2023/08/31
bapaksejahtera
15
発酵学の権威乍ら親しみ易い説明で知られる学者が書いた日本の酒に関する本。町の酒屋の壊滅等、30年前の初刊からの世の中の変化はあるが、我が国の酒造史を考古学や発酵学の知識等を基に漏れ無く辿る。山葡萄等漿果類からの酒、堅果や穀物澱粉のα化後の麹菌利用から始まる我が国の酒の科学史が始まる。我が国独自の技術革新に関与した仏寺での酒の低温処理は、パスツールに数世紀先行する。造り酒屋の発展と灘や伏見からの下り酒。酒樽、酒造用の桶の他、酒の民俗・文化記述は漏れがない。灰を混ぜたのが清酒の成立という俗信の誤り指摘も嬉しい2025/03/23
ikedajack
6
日本独自の文化である日本酒。20年前の本を文庫化した一冊だが、日本酒の歴史を細かく分かりやすく描いています。日本酒は飲み物だけでなく、日本ならではの米、水、麹をうまく活用した昔からの伝統の賜物であることがよく分かりました。2022/07/07