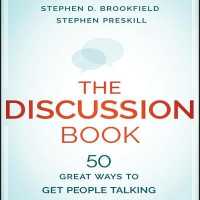出版社内容情報
宇野 重規[ウノ シゲキ]
著・文・その他
内容説明
今や危機に瀕した民主主義、まだ可能性はあるのか?過去をたどり未来への答えを導く!
目次
序 民主主義の危機
第1章 民主主義の「誕生」
第2章 ヨーロッパへの「継承」
第3章 自由主義との「結合」
第4章 民主主義の「実現」
第5章 日本の民主主義
結び 民主主義の未来
著者等紹介
宇野重規[ウノシゲキ]
1967年、東京都生まれ。東京大学法学部卒業。同大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。現在、東京大学社会科学研究所教授。専攻は政治思想史、政治哲学。主な著書に『政治哲学へ 現代フランスとの対話』(2004年渋沢・クローデル賞LVJ特別賞受賞)、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社学術文庫、2007年サントリー学芸賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
178
古代ギリシア以来の民主主義の歴史を「参加と責任のシステム」の視点から辿る。「公共の利益を支配」する共和政に対して「多数の利益を支配」する民主政は最近まで侮蔑されてきた。思想家を引用しながらの各国の転機や、議会制や自由主義との関係も丁寧に解説。透明性・当事者意識・責任を希薄化する議会制の弊害やポピュリズム・格差拡大の温床を指摘しつつ、主体性・多様性を許容する民主主義の紆余曲折を評価することで批判に反論。変質は悪いことばかりではない、常に在り方を問うのが民主主義の意義。これからを考えるために過去を整理した書。2022/11/13
trazom
156
とても考えさせられる一冊。共和政と違って、2500年の歴史の中で民主政は常に否定的な言葉だった。一般意志のルソー、能動的市民と受動的市民を区別したシェイエス、米国のデモクラシーを評価したトクヴィル、代議制民主主義のミルらの理論構築を経て、ウェーバーやフロムの懐疑論に繋がり、「責任と参加のシステム」である民主主義が空洞化した現実が語られる。その原因は、代議制などの制度ではなく、ルソーが「一人一人が社会全体の公共の利益を考える」と仮定した前提を有名無実化させてしまった現代の私たち自身にあると思えて仕方ない。2021/01/11
ひろき@巨人の肩
134
民主主義とは、参加と責任の政治システム。少数派を尊重しつつ多数決で意思決定する。群衆による判断は時間がかかり、時に過ちを犯すが、当事者意識が生まれ多様性のある共同体を形成できる。歴史は古く2500年前に古代ギリシアで直接民主主義が発生。その後は200年前まで君主制・共和制のアンチテーゼとして捉えられた。現代の代議制民主主義は間接民主主義であり、西欧諸国が成功例として、自由主義や資本主義の必要条件として結びつけるため、定義や理念に曖昧さが生まれる。また立法への参加に加え、行政への参加を検討する必要あり。2021/10/01
遥かなる想い
127
2021年新書大賞第2位。 わかっているようで 実はわかっていない 「民主主義」の本である。 民主主義という正体のつかみにくいものを 歴史的に 解説してくれる。 古代ギリシアから 現代に至る 流れを 民主主義という視点で 語られ、興味深い。2021/07/13
けんとまん1007
121
民主主義と、当たり前のように言っているが、説明しなさい・・と、言われると、できないのが事実。そんな民主主義を、基本から丁寧に述べられていて、とても良い本だと思う。ギリシャの時代から、今日に至るまで、歴史の変遷とともに、どう考えられ、どう変わってきたのか。決して望ましい時代ばかりではなかったのも、理解が深まる。自由主義と民主主義の意味合いを考えると、とても興味深い。それが、世界だけなく、今の日本の現状を考えるのにも、貴重な指針となる。2021/06/27
-
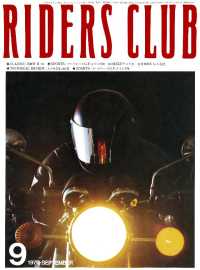
- 電子書籍
- RIDERS CLUB No.15 1…