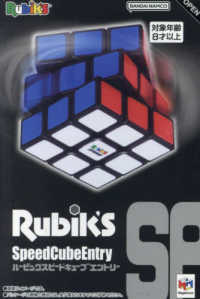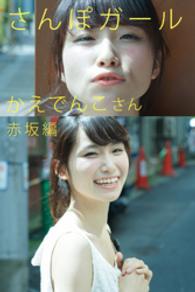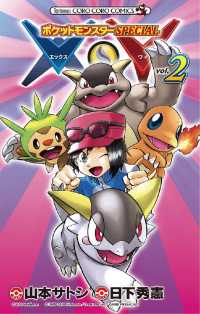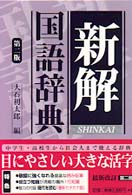出版社内容情報
本書は,分光分析法を利用する材料研究者(=ユーザー)へ向けて,問題解決のためにどのように分光分析法を選択・利用すべきかを解説した新しいアプローチの本である。
第1章で材料の分光分析について概観した後、第2章ではどのような考え方に基づいて各種の分光分析法を選択すべきかを解説した。具体的には,2.1節では組成分析,状態分析,構造分析など分析目的から分光分析法を選択する場合を,2.2節では分析対象のサイズ(局所分析)や存在量(微量分析)に着目して分光分析法を選択する場合を記述した。2.3節では材料の立場に立った分光分析法の選択フローを解説し,2.4節では分光分析法を複合的に適用する必要性と分光分析法の標準化を活用・推進する意義を解説した。
第3章ではさまざまな材料を具体的に取り上げ,課題解決のためにどのような分光分析法が適用されたかを具体的に紹介した。材料としては「金属材料」「半導体材料」「有機化合物材料」「無機化合物材料」に加え,展開用途に着目したトピックス的な材料として「電池材料」「セラミックス材料」「磁性薄膜(磁気デバイス)材料」「複合材料」を取り上げ,分光分析法の適用事例を紹介した。
最後の第4章においては,第3章で利用された各種の分光分析法の原理・特徴や適用上の問題点について,電子を利用した分光分析法(4.1節),X線・光を利用した分光分析法(4.2節),イオン・中性粒子を利用した分光分析法(4.3節)の3つの分類に分けて解説した。
手元の材料をどのようにして分析すべきか,その全体像がわかる1冊で,本書を読めば研究をより有意義かつ効率的に進められることは確実である。材料研究者にはぜひお薦めしたい。
目次
第1章 本書のねらい
第2章 分光分析法の選択に向けて(分析目的にもとづく分光分析法の選択;分析対象にもとづく分光分析法の選択;材料の種類にもとづく分光分析法の選択;複合化と標準化)
第3章 材料研究への分光法の適用―事例に学ぶ(金属材料;半導体材料;磁性薄膜(磁気デバイス)材料
有機化合物材料
触媒材料
セラミックス材料
電池材料)
第4章 分光法各論(電子を利用した分光分析法;X線・光を利用した分光分析法;イオン・中性粒子を利用した分光分析法)
著者等紹介
一村信吾[イチムラシンゴ]
工学博士。1981年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士課程修了。現在、早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略部門教授
橋本哲[ハシモトサトシ]
博士(工学)。1982年東北大学大学院理学研究科物理学専攻修士課程修了。現在、JFEテクノリサーチ(株)営業本部/機能材料ソリューション本部ナノ解析センター専門技監
飯島善時[イイジマヨシトキ]
博士(工学)。1995年山梨大学大学院工学研究科物質工学専攻博士後期課程修了。現在、東京農工大学学術研究支援総合センター設備サポート室(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。