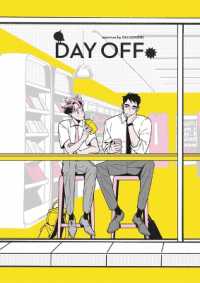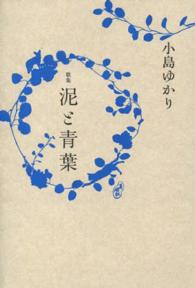出版社内容情報
躓きの石としての天皇 超克されざる「近代」
――近代日本のパラドクス
革命への赤き心は、なにゆえ脱臼され、無限の現状肯定へと転化されなければならないのか。躓きの石としての天皇、超克されざる「近代」――北一輝から蓑田胸喜まで、西田幾多郎から長谷川如是閑まで、大正・昭和前期の思想家たちを巻き込み、総無責任化、無思想化へと雪崩を打って向かってゆく、近代日本思想極北への歩みを描く。
[本書の内容]
●「超―国家主義」と「超国家―主義」
●万世一系と「永遠の今」
●動と静の逆ユートピア
●「口舌の徒」安岡正篤
●西田幾多郎の「慰安の途」
●アンポンタン・ポカン君の思想
●現人神
目次
第1章 右翼と革命
――世の中を変えようとする、だがうまくゆかない
第2章 右翼と教養主義
――どうせうまく変えられないならば、自分で変えようとは
思わないようにする
第3章 右翼と時間
――変えることを諦めれば、現在のあるがままを受け入れたくなってくる
第4章 右翼と身体
――すべてを受け入れて頭で考えることがなくなれば、からだだけが残る
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
23
右翼と保守は実は全く違う、現状を否定し、あるべき理想の姿を過去に求めるのが右翼で未来に求めるのが左翼、この整理がとてもわかりやすい。「保守」とされる勢力が最も急進的というねじれの構図は日本だけではないけれど、日本の右翼の場合、否定すべき現在と理想の過去がともに同じ天皇を抱いている、そのことでもう一段ややこしさが深まる。超国家主義にせよネトウヨにせよ、対話の成立のしにくさはこれが原因だな。◇そう考えると、右翼からはヌルいとされる安岡正篤が魅力的に見えてくる。終戦直後の宮本常一が仕事していた理由が腑に落ちる。2014/04/24
amanon
12
思った以上に興味深い内容。これまで毛嫌いしていた右翼的ものに対する印象が多少なりとも払拭された感が。それと同時に、今ネトウヨと呼ばれている人達が愛国という立場を取っている他は、大凡右翼という名前に値しないゴロツキでしかないということを改めて痛感。以前読んだ佐藤優との共著でも、戦前日本社会のタコ壷的なあり方が指摘されていたが、本書でもやや違った視点でそのことについて触れているのが印象的。そして、右翼思想にとって最大の拠り所でありながら、そこを突き詰めていくと矛盾が生じてしまう天皇の厄介さについても再認識。2020/07/18
amanon
11
同じ本をこれ程短いスパンで再読するのは、かなり珍しいことだが、再読して良かったと痛感。初読では見えなかったことが予想以上に見えるようになった。また、とんでも愛国論を振りまくネトウヨと呼ばれる連中が大凡右翼と呼ばれるに値しない浅薄で軽薄極まりない輩であることを改めて痛感。だからこそ本書は読まれなければならない。また、右翼というとやたら強面なイメージがあるが、それはあくまで一面的なものだということは強調すべき。ただ、多種多様なあり方があったはずの右翼が日本崩壊へと導く結果に至らす原動力になったのが残念。2020/08/05
かんがく
11
戦前日本の「右翼」と呼ばれる人々の様々な思想を記述。 「左翼(未来)、中道(漸進)=保守(現在)、右翼(過去)=反動」という整理。右翼と一言で称しても、大川周明のようなアジア主義者、北一輝のような超国家主義者、権藤成卿のような農本主義者など様々いることがわかった。とにかく天皇というものがそこかしこで出てくるが、その評価もそれぞれ異なる。天皇が理想でありながら現実でもあるという矛盾。革命を目指す思想から、現在「中今」を維持する思想へ。様々な分野の書物、人物が次々に出てきてかなり面白い思想史だった。2018/07/12
無重力蜜柑
10
めちゃくちゃ面白い。片山杜秀は『未完のファシズム』に続き二冊めだが、やはり思想史としてのストーリーが唯一無二という印象がある。それは後書きでも触れられている右翼に対する彼の一種のシンパシー(現代日本の人文系アカデミアでは絶滅危惧種に等しい素質だ)の賜物だろう。大正から敗戦までの「右翼思想」を語る本書が、有名どころの右翼ではなく一般に右翼と見なされない思想家や超マイナー思想家を挙げるのも、筆者自身が語りたい「右翼思想」が既に固まっているからだ。無論、「実証性」は欠片もないが、思想史はそのくらいでいいと思う。2024/11/28
-

- 文具・雑貨・特選品
- ジュエリー絵画(R) 手塚治虫 ブラッ…