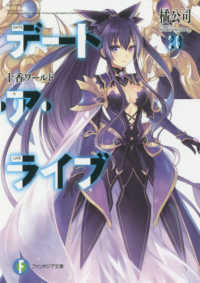内容説明
屍を乗り越えてすすむ坂東武者。文弱の平家の公達。こうしたイメージは本当なのだろうか。騎馬戦の不得手な武士、兵粮徴発をこばむ百姓…。「平家物語史観」に修正をせまり、内乱が生んだ異形の権力=鎌倉幕府の成立を鋭く解明する。
目次
第1章 武士再考
第2章 「弓馬の道」の実相
第3章 源平の「総力戦」
第4章 飢饉のなかの兵粮調達
第5章 鎌倉幕府権力の形成
第6章 奥州合戦
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
大竹 粋
6
平家物語史観ではなく、内乱の収拾としての新政権樹立という筋。現実的な戦争の内実が見事に面白い読み物にもなっていて、ますます今の日本の原型が形作られたこの時代に魅了される。2022/05/11
Kamabonz
4
古い資料ですが ①武士の起源が最新かつ特殊スキルを身につけた職業軍人としたこと ②『驕れる平家は久しからず』というほど驕ってはいなかったこと ③頼朝は自身の正当性を確保するのにかなり苦労したこと ④奥州藤原氏(鎮守府将軍)を超える官職のために征夷大将軍を欲した などの発見があってとても面白かったです。 このカテゴリの最新の知見を知りたくなりました。2020/11/05
遊未
4
日本史では初めて読んだが、この時代の軍隊についての研究。平家物語に多い「組打ち」は新しい形であり、本来の武士の技能は騎射であった。しかし、当時の馬は小さく、「生飡」のような名馬は大きかったようです。兵糧はやはり大きな問題で、「方丈記」にある異常気象、飢饉と同時代であったことがわかります。いつの時代もですが、兵站はどうなっていたのでしょうか。2015/11/18
印度 洋一郎
4
絵巻物のような源平合戦の実像を軍事的に考察。元々、平安時代の武士は階級では無く、戦闘技術を持つ職能だった。しかし、その専門性の高さから階級化したのだという。その戦士階級が初めて激突した源平の戦いは、当時の日本全域が戦場となった日本史初の全面的内戦だった。数千から数万の兵力を動員し、ポニーのような小型の馬に乗って至近距離から弓で撃ち合い、斬りかかる近接戦闘、交通路をふさぐバリケードから始まった”城”、そして対騎馬壕である”堀”の発達など興味深い。対平家戦よりも奥州攻めの方が大合戦だったという考察も面白い。2010/09/29
鳥山仁@『純粋娯楽創作理論 第二章』発売
3
二十年ぶりぐらいに買い直して読んだが、やはり面白い内容だった。盛者必衰、負ける側には必然性があると言う、『平家物語史観』の批判から入り、当時の戦闘形式の変化に言及するなど、ファンタジー好きな人には今でも読んで損の無い内容だと思う。2019/09/14