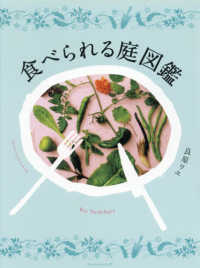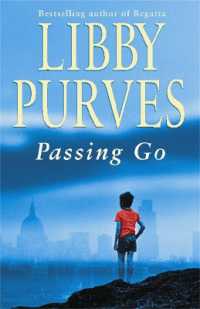出版社内容情報
中国の版図は海洋に向かう。南シナ海の地下資源・海洋資源の争奪戦が始まった! 地政学アナリストが占う危険な中国の野望とアジア。南シナ海は、地下資源もさることながらインド洋と東シナ海、日本海を結ぶ世界の大動脈。海洋大国をめざす中国が、南シナ海の覇権を奪取しようとして、周辺諸国と一触即発の状態になっている。
すでに国力の貧弱なフィリピンは完全に見下され、スプラトリー諸島を戦火を交えることなく中国に奪われた。
だが、南シナ海周辺諸国には経済力のあるシンガポールや台湾、マレーシア、中国を恐れぬ国ベトナムなど強敵がひしめいている。
「ストラトフォー」地政学チーフアナリストのロバート・D・カプランが、周辺国を歩いてつぶさに観察し、現地の学者や政治家に取材して、今後の南シナ海情勢を予測する。
マーティン・デンプシー米統合参謀本部議長絶賛!
プロローグ チャンパ遺跡で考えたこと
第1章 人道・平和主義者のジレンマ
第2章 中国のカリブ海
第3章 ベトナムの行く末
第4章 文明入り混じるマレーシア
第5章 「よい独裁者」がいる都市国家シンガポール
第6章 植民地時代の重荷に苦しむフィリピン
第7章 アジアのベルリン・台湾
第8章 北京の思惑
エピローグ ボルネオ島のスラム街
ロバート.D・カプラン[ロバート.D カプラン]
著・文・その他
奥山 真司[オクヤマ マサシ]
翻訳
内容説明
世界の海上交通ルートの要衝にして天然資源豊富な南シナ海を狙う中国。気鋭の地政学アナリストが読み解く、赤い帝国の脅威。
目次
プロローグ チャンパ遺跡で考えたこと
第1章 人道・平和主義者のジレンマ
第2章 中国のカリブ海
第3章 ベトナムの行く末
第4章 文明入り混じるマレーシア
第5章 「よい独裁者」がいる都市国家シンガポール
第6章 植民地時代の重荷に苦しむフィリピン
第7章 アジアのベルリン・台湾
第8章 北京の思惑
エピローグ ボルネオ島のスラム街
著者等紹介
カプラン,ロバート・D.[カプラン,ロバートD.] [Kaplan,Robert D.]
世界的なインテリジェンス企業、米ストラトフォーのチーフ地政学アナリストのほか、ワシントンのシンクタンク「新米国安全保障センター」の上級研究員や、高級誌である『アトランティック』誌の外交・安全保障担当記者を長年務める、フリーランスの国際ジャーナリスト。米政権ブレーンとして国防総省・防衛政策協議会のアドバイザーも歴任。2012年には、『フォーリン・ポリシー』誌による「100人のグローバルな思索家」に選出される
奥山真司[オクヤママサシ]
国際地政学研究所上席研究員、海上自衛隊幹部学校客員研究員、青山学院大学非常勤講師。カナダ、ブリティッシュ・コロンビア大学卒業。英国レディング大学大学院博士課程修了。戦略学博士(Ph.D)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。