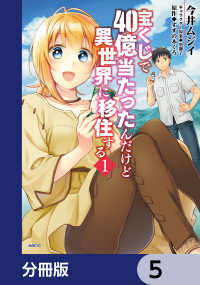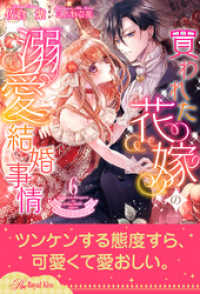内容説明
日本近代の“欧化”の象徴としての鹿鳴館―。その華やかさのうしろにある“悲哀”を見出す著者が、近代日本百年の歩みを、そのヴァリエーションとして、再構成しながら、社会・風俗・建築・音楽など、文化の全領域に“欧化という伝統”を発掘。既成の文学史観を覆す知的スリルに満ちた長篇。磯田光一の代表的エッセイ。読売文学賞受賞。
目次
1 訳語「文学」の誕生―西と東の交点
2 「小学唱歌」考―その一世紀の帰趨
3 湯島天神と丸善―硯友社における江戸と西洋
4 東京外国語学校の位置―二葉亭四迷『浮雲』の原像
5 「明星」派の水脈―『みだれ髪』の遺産
6 漱石山房の内と外―『明暗』の基底にあるもの
7 『田園の憂鬱』の周辺―佐藤春夫と宇野浩二
8 日比谷・銀座界隅―都市と前衛芸術
9 「革命」という外来思想―風土のなかのドラマ
10 昭和のモダニズム―ある感情革命
11 三人の鹿鳴館演出者―聖徳太子・伊藤博文・吉田茂
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
10
明治から昭和初期にかけて、近代日本における「欧化の伝統」を見出す。その際に象徴となるのが鹿鳴館。「貧しさ」を見繕う建築物として、唱歌も、翻訳語も、学校も作られていく。マルクス主義の導入も、欧化の見繕い、つまり「鹿鳴館」の一種である。最終章で聖徳太子・伊藤博文・吉田茂をつなぐ論を提示し、奈良時代から現代までをひとつの系譜で連ねるイメージで全体を締める。刊行は1983年。『構造と力』と同じ年の刊行だが、ニューアカとはやはり距離がある。なにより、資本主義や伝統からの「逃走=闘争」という視点は一切導入されない。2022/10/21
Lieu
2
文化史や都市論を織り込んだ、「欧化」を巡る近代日本文学論。萩原恭次郎の詩と大正期の交通量の推移の関係などを論じる「日比谷・銀座界隈」が特に面白かった。2020/01/23
AR読書記録
2
これも読む前にこちらに準備(知識・教養)がないと、味読は難しい内容ではある。が、切り口に意表を突かれる感じ、予想外のキーワードが自在に現れる様子には、すごくわくわくする気持ちが呼び起こされて、これを実感をこめて「確かに、私もそう思った!」とか感じながら読めたら、ほんとうに“知的スリルに満ちた”読書体験として楽しめると思う。あとがきも読みつつ、著者の思想、視点は私も追随したいところと思うので、時間をかけてでもじっくり今後も向き合っていこうっと。2014/09/21