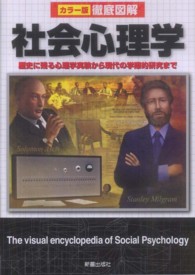内容説明
規制撤廃、産業再編成、市場第一主義―グローバライゼーションは人々に何をもたらすか。経済社会で進行する変化と淘汰を新たな視点から読む。
目次
第1章 進化する社会(ラマルクの進化論;マルサスの人口論;『種の起源』のインパクト;スペンサーの進化論;ヴェブレンの制度進化論;ハイエクの進化論;経済学における「進化」の定義)
第2章 経済進化と知識(モノ作りの知識;企業の理論;産業の理論;政策の理論)
第3章 知識・制度・人間(知識とコミュニケーション;知識とは何か)
第4章 経済と経済以外のもの(制度疲労と改革;グローバライゼーションの流れの中で;経済と幸福)
著者等紹介
江頭進[エガシラススム]
1966年愛媛県生まれ。京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士。専攻は経済学史。現在、小樽商科大学経済学科助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kei
13
今でこそ、シカゴ大学、スタンフォード大学はトップレベルの大学として知られているが、当時は両大学とも創立してそれほど年月がたっておらず、むしろ市場を独占することによって成り上がった新興の金持ちたちが、偽善的に設立した大学であると見られて評価は高くなかったのである(45頁)。人間は有用性や効率性を高く評価し、不毛性、浪費すなわち無能さを低く評価する、という感覚をもっている。この習性あるいは性向は製作者本能と呼ぶことができよう。2016/09/28
ひつまぶし
3
面白かったけど、進化経済学は進化心理学や進化生物学のような意味での進化論の応用ではなかった。経済学が経済学のまま社会学的な発想を取り入れようとすると「進化論」を名乗るほどの大ぶりが必要になるということかと思った。スペンサーやコント、そしてデュルケムまで言及していて、そう考えるともともと社会学は「進化社会学」とでもいうべき学問なのだろう。個人間での知識の伝播と共有、そこに影響を及ぼす社会制度といった整理はそれなりに面白い。スペンサー、ヴェブレン、ハイエクほか、いろんな論者の影響関係が分かるのも良かった。2025/10/21
1.3manen
1
レギュラシオン理論など、制度経済学に興味があったので、買ってみた。ヴェブレンや、アマルティア・センが登場し、新古典派経済学や市場原理主義の見落としてしまった制度や法律や政策などの意義が感じられる分野。2012/04/09
sk
0
んー、なんていうか体系が整っていない感じ。2013/10/26
-
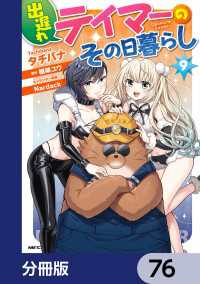
- 電子書籍
- 出遅れテイマーのその日暮らし【分冊版】…
-

- 電子書籍
- ライデン 暴走変身宅配野郎 イン マレ…