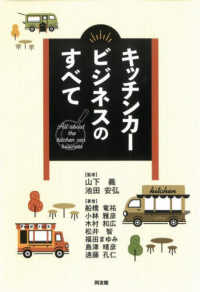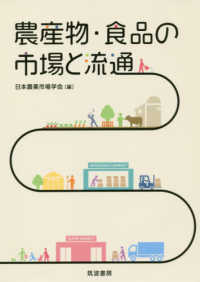内容説明
戦後社会の歴史と仕組みを経済の視点から読み解く池上彰の「経済学」講義。東西冷戦、日本の戦後の歩みなど、歴史に学ぶことで未来が見える。愛知学院大学2014年講義書籍化!第1弾。
目次
プロローグ 経済学を学ぶということ
1 経済、そして経済学とはそもそも何か
2 廃墟から立ち上がった日本
3 東西冷戦の中の日本
4 日本はなぜ高度経済成長を実現できたのか
5 高度経済成長の歪み―公害問題が噴出した
6 バブルが生まれ、はじけた
7 社会主義の失敗と教訓―ソ連、東欧、北朝鮮
8 中国の失敗と発展
著者等紹介
池上彰[イケガミアキラ]
ジャーナリスト、東京工業大学教授、愛知学院大学経済学部特任教授。1950年、長野県生まれ。慶應義塾大学卒業後、1973年にNHK入局。1994年から11年間、「週刊こどもニュース」のお父さん役として活躍。2005年よりフリーに(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
HIRO1970
65
⭐️⭐️⭐️実家借用本。池上さんいつもながら解りやすい素晴らしい本でした。中3の長男にも読ませようと思います。この本は表題のタイトルにて愛知学院大で著者が行った15回の講義を纏めたものです。テレビ東京系列で放映もしたので違う媒体でご覧になったかたも多いでしょう。歴史的な出来事の背景は何か、具体的には何がきっかけなのか?それが今にどんな風に影響しているのか?戦後70年の世界経済の歩みがたった一冊の本で学べるのは幸福な恵みですらあります。皆さんにオススメです。2015/06/14
みゃーこ
60
経済は動くものではないということ。経済は命令や号令をかければ動くというものではないということです。大勢の参加者の思惑によって動いていく、これが経済行動だ、と言うこと。そう言うことを知らない]戦後史の経済政策の失敗と成功を振り返り総括する。共産主義と社会主義の違いを知り、理想と現実のギャップを埋めるための模索を人類はどこまで深めていくことができるかが課題であるかに思える。2015/11/17
壱萬参仟縁
36
厚いが、ゴシ太本なのでそれほど大変ではないと思う。経済学とは、資源の最適配分を考える学問である(22頁)。つまり、政治経済学といえばよいと思う。不合理もやる人間の真理をきちっと踏まえて経済学は世の中を分析するツールとして役に立つ(40頁)。時代によって、常にその時代に合った業態、仕事を見つけていかないと、生き延びていくことはできない(87頁)。初めての国民車はすばる360。続いてホンダ360(182頁)。2015/10/14
べっち
34
★★★★★2015年一冊目。池上彰さんの本は何冊か読んだが今回の本が一番お気に入り。復習のつもりで読んだがまだまだ知らないこともたくさんあり、大変勉強になった。上に立つ者の思想や能力、体制や構造でいかに組織やその中の人々に影響を及ぼすか、、、改めて選挙の大切さや上に立つ者の責任の重要さを考えさせられた。 また、いかに人の心理が経済や政治に影響を及ぶか、、心理学も勉強してみたい。「歴史は人の営みの積み重ね。単なる暗記科目ではなく、非常に論理的なもの。」だからこそ学ぶ意義がある。2015/01/01
えっくん
30
★★★★☆日本の高度成長と公害問題、バブル崩壊、社会主義体制の崩壊、中国の失敗と発展など愛知学院大学での講義を書籍化した本です。講義中に使用されている資料映像が見られないのがいくつかあったのが残念ですが、教科書にも載っていないような興味深い講義内容を読んで大変勉強になりました。北朝鮮との戦争に備えソウル市内の橋には爆薬が仕掛けられ今も戦争が終わっていないこと、日本の高度成長期の環境汚染を隠ぺいし続けた企業体質、中国の誤まった大躍進政策が生産性の低下を招き餓死や黄砂が発生したことなど驚きの内容が満載でした。2017/05/06