内容説明
2013年に話題となった神奈川県横浜市の待機児童ゼロ達成。実はこれにはウラがあった―。保育所の補助金や児童館、学童保育、そして予防接種ひとつをとっても、すべて国会や地域の議会で決められる。子育てと政治は密接な関係にあるのだ。子育ての現場を長年取材してきた著者が、「子育てとそれに対する政治の対応」を多くのデータを交えながら検証し、日本の子育てを考える。保育新制度の中身と問題点にも触れる関係者必読の書。
目次
第1章 横浜市「待機児童ゼロ」の真実
第2章 「待機児童」の歴史
第3章 待機児童はなぜ生まれるのか?
第4章 待機児童と保育事故
第5章 「保活」の現実
第6章 「待機児童一揆」はなぜ起こる?
第7章 保育士不足と待機児童
第8章 保育所という「命綱」
第9章 保育新制度は子育て世代を幸せにするか?
著者等紹介
猪熊弘子[イノクマヒロコ]
ジャーナリスト・東京都市大学客員准教授。日本女子大学卒。主に就学前の子どもの福祉や教育、女性や家族の問題を中心に取材・執筆、翻訳。特に保育制度・政策、保育施設での事故について詳しい。『死を招いた保育』(ひとなる書房)で、日本保育学会第49回日私幼賞・保育学文献賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スノーシェルター
20
少子化になっているはずなのに、待機児童が増えるのは何故?と思っていたので読んでみた。横浜の待機児童ゼロも数字トリック。政治家は耳障りの良いことばかり言うけれど、現実を把握していないし、昔とは社会環境が違う。雇用や貧困を解決しないと子育てのしにくい国になるばかり。親の便利は子の不便に納得。2014/08/29
melon
17
保育の仕事は「感情労働」。 人と接することへの喜びを感じられない職場では、続けていくことができない。 保育士は子どもと目を合わせ子どもの信頼を受けてはじめて成立する仕事。保育士は子ども一人ひとりを見て、この子にこんな力をつけてあげたい、それにはどうすればいいかと考えている。人員が足りない中できちんとそれらをやろうとすると時間が足りなく、みんなそれで燃え尽きる。2014/10/02
非日常口
17
Amazonの評価が低いのも納得。高評価で売れたら横浜は困るだろう。ニートの数が減ったみたいなニュースがあったが、定義が34歳までなだけで35歳からそういう人が就職するとも思えず数字のマジックが見え隠れする。待機児童の問題もどうやら同様で、カウントされないような、また受け入れるキャパを無理に広げるようなマジックがあったらしい。コミュニティが破断してきている都市において、そのフォローもなく共働き世代を増やす政策も問題ある気がする。子供はモノではないのに効率化という名で質より量の犠牲になっていくようだ。2014/08/08
ゆう。
12
保育を受ける権利が乳幼児期の子どもたちにあることを前提に、待機児童問題とは何なのかを丁寧な取材などを通してせまった本です。題名に「政治」と使われているように、著者は保育や子育ては政治的であることを訴えます。なぜなら、世論を動かし、予算を獲得し、子どもたちの権利を守ることは、鋭く政治的だからです。また、待機児童が生まれることは、児童福祉法違反であることもわかります。そして、待機児童をただ数の上だけ減らせばよいと、保育の質や保育者の専門性がおろそかにされている実態もよくわかると思います。良書です。2014/08/05
人間
8
待機児童問題が解消に至らない根本はどこにあるのか。日本には就学前の子供のための権利が、憲法はじめ他の法律にも一切記載がないという。児童福祉法には市町村は保育に欠ける子供を保育しなければならない、とあるけども、子供が子供らしく過ごす権利はどこにも明記されていないそうで、これには驚いた。規制緩和によって下がる保育園の質も、保育園に入所できず貧困家庭に陥るあおりも、結局すべて子どもにしわ寄せがいく。憲法改正するなら子供の権利を記載すべき。とても勉強になる本だった。2019/03/28
-

- 電子書籍
- 揶揄わないでよお義母さん~罪悪感は快楽…
-
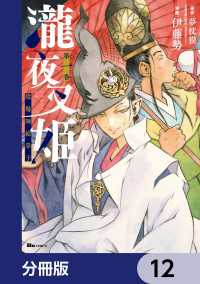
- 電子書籍
- 瀧夜叉姫 陰陽師絵草子【分冊版】 12…
-

- 電子書籍
- 甦!戦馬大戦27【タテヨミ】
-

- 電子書籍
- 宮田光雄思想史論集2:キリスト教思想史…
-

- 電子書籍
- 七緒 2020 夏号vol.62




