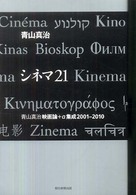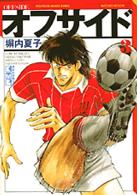出版社内容情報
神話を下敷きにしたジョイス、ハードボイルドなチャンドラー、「方法」を提唱したヴァレリー。彼らは日々の生活を作品に昇華させた。19世紀後半~20世紀前半の世界文学史を転換させた名作を一気に紹介。
目次
第1章 近代の咆哮(ナサニエル・ホーソーン『緋文字』一四七四夜;ハーマン・メルヴィル『白鯨』三〇〇夜 ほか)
第2章 作家たちの方法(フランツ・カフカ『城』六四夜;アルフレッド・ジャリ『超男性』三四夜 ほか)
第3章 欲望と事件(フランソワ・モーリアック『テレーズ・デスケルウ』三七三夜;デイヴィッド・ハーバート・ロレンス『チャタレイ夫人の恋人』八五五夜 ほか)
第4章 奥の疼き(ボリス・ヴィアン『日々の泡』二一夜;トルーマン・カポーティ『遠い声 遠い部屋』三八夜 ほか)
追伸 方法が作品から零れ落ちている
著者等紹介
松岡正剛[マツオカセイゴウ]
編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。情報文化と情報技術をつなぐ方法論を体系化した「編集工学」を確立、様々なプロジェクトに応用する。2000年「千夜千冊」の連載を開始。同年、eラーニングの先駆けともなる「イシス編集学校」をネット上に開校し、約600名の師範代を育成。編集術とともに世界読書術を広く伝授している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





読書という航海の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
101
前巻に引き続いて世界文学の作品オンパレードです。比較的近代のものが多くわたしにはなじみの(読んだ)本がかなり多くありました。他の千夜千冊よりもわかりやすく読んでいてすんなり頭に入ってきます。ただやはりかなり凝った読み方で一つの作品でも参照文献がかなり多くあります。私などは及びもつかないのですが、このような観点もあるのかということで再度読みたくなる本がかなり多くありました。2020/11/07
まこみや
18
“読書というもの、「入口」においてはいつだって孤独な探索になる。誰もが一人ずつの一代の過客として名のりをあげていくしかない。しかしながらその「出口」からはシナジェティックな共感が百代百人の過客として放射状に広がっていく。”(p396)ここに紹介されている本はいずれも著名なものばかりだ。しかし私自身初めから終いまで通読したものはわずかしかないと今更ながら気がついた。何事も始めるに遅いことはないと信じて、手始めにガルシア・マルケス『百年の孤独』から始めよう。2021/04/01
ほんままこと
16
松岡正剛さんが亡くなられたというニュース。とても残念。この本は、電車に乗るときなどに持って行き、一つの作品の書評を読み、すっかりその本を読んだ気分になる満足感があった。文章もうまく、一つの作品を取り巻く知識と教養の深さに感嘆する。筆者の身辺雑記的なことも書かれていて、好奇心も満足させられる。そしてこれは文庫本なのだが、非常に凝った作り方をしている。装丁や活字の種類、帯まで。ご冥福を祈るのみ。2024/08/27
ハルト
11
読了:◎ 圧巻の読書量と知識量。十九世紀後半から二十世紀前半の作家たちの作品を原作の刊行順に構成した本書。読書エッセイ、参考書としておもしろく読めた。多角的視野で一冊一冊を分解しての独特の語り口は、癖になる。本書に取り上げられた本を読んでから、またこの本を読んでみたいと思った。2021/02/23
袖崎いたる
9
パラパラ読みするつもりが、つい耽ってしまった。よくもまぁ知っておりまんなぁといった情報過多とそれを編集する手管は大したモノ。ジョイスの『ダブリンの人びと』を語った〆の一節に、「ブンガクは心理学ではなく言葉の病理学だ。イメージの細菌学だ。」(p187-188)とあったのは思わず膝を叩きたくなった。ラカン派の精神科医・斎藤環あたりは「文学は関係性の科学」だとか、「精神分析だけが個人の潜在性をかろうじて扱えるのだ」なんて語っていたけど、きっと彼もニヤッとさせられるのではないかしら。ごちそうさま。2020/12/15



![CDリスニング要件・効果 〈7〉 行政法 [CD+テキスト] (第2版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/49045/4904520793.jpg)