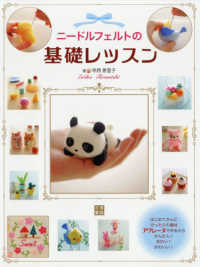内容説明
紫式部が、藤原道長の娘、中宮彰子に仕えた際の回想録。史書からは窺えない宮廷行事の様子もわかり、道長が全権を掌握する前夜という緊張に満ちた状況下での記述が興味深い。華麗な生活から距離を置く紫式部の心理や、実務をこなせない同僚女房への冷静な評価、ライバル清少納言への辛口批評などが描かれる。精密な校訂による本文、詳細な注、流麗な現代語訳、歴史的事実を押さえた解説で、『源氏物語』の背景を伝える日記のすべてがわかる。
目次
出産の秋、到来―中宮の姿
朝霧の中の贈答―道長の威風
しめやかなる夕暮れ―若き頼通の雅
八月―待機する貴顕たち
八月二十六日―若宮乳母の美しさ
九月九日朝―中宮の母倫子の気遣い
九月九日夜―兆し
九月十日―御産始まる
九月十一日未明―大事を見守る人々
九月十一日午の刻―男子誕生〔ほか〕
著者等紹介
紫式部[ムラサキシキブ]
生没年未詳。970年代の生まれか。『源氏物語』『紫式部日記』作者、家集に『紫式部集』があり、『後拾遺和歌集』初出の勅撰集歌人。中古三十六歌仙の一人
山本淳子[ヤマモトジュンコ]
1960年石川県生まれ。京都大学大学院博士課程修了。高等学校教諭の経験のあとに大学院に入り、金沢大学などの非常勤講師を経て京都学園大学教授。著書に、『源氏物語の時代―一条天皇と后たちのものがたり』(朝日選書、サントリー学芸賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
74
興味深い1冊でした。華やかな世界から離れ、才女として評価された紫式部。ただ、貴族社会に入ろうとすればするほど、何かが失われるのだと思いました。同僚女性を冷静に見つめ、清少納言に辛口を言うこと自体、冷淡な一面も持ち合わせていたのかと思いました。2019/05/12
がらくたどん
64
学生時代『枕草子』に比べて華がない・根昏いとイマイチ人気がなかった『紫式部日記』大河のキュートな式部ちゃんに励まされ大好きな山本先生の訳注で再挑戦。文体は「源氏」より平易直截でメインの中宮彰子のお産記録などは「女房は見た!これが中宮のお産だ(道長全面バックアップ)」みたいでとても面白い事に気づく。全節を前期記録(~49)消息体(手紙)(~60)日付不明記録(~63)後期記録(~69)に分けて読むことで中年逃げ腰女房が誰か(多分娘の賢子)に女房心得を残せるほどのプロ女房へと進化する過程が見えてくる。→2024/03/14
しゅてふぁん
38
華やかな行事の様子を書いていても、最終的には我が身の嘆きや愚痴になっていって、紫式部が根暗と言われる所以がここにあるのかしらと思えてきて面白い。たとえ権力者の意図に沿うような内容であったとしても、当時の宮中の様子や人々の評判を窺い知ることができるのは凄いことだと思った。2018/02/05
tsu55
30
NHKの『光る君』に触発されて。 大河ドラマはどうも肌が合わないのだけれど、今年は武将や政治家といったエライ人じゃなくて、紫式部が主役ということなので、毎週楽しく観ている。 祝宴の席で乱れる公卿だとか、宮廷でのいじめとか、歴史の教科書ではわからない、公卿や女房達の素顔が描かれていて興味深い。 一見構成が雑な感じがするのは、出仕する娘のために手元の草稿を寄せ集めて、女房としての心得を伝えようとしたのだとしたら、納得がいく。2024/04/10
yumiha
23
現代語訳なしぢゃ手も足も出ませぬ。でも原文ではどんな表現かしらん?と確かめたい人向きの本書。中宮彰子の出産を記録した準公文書的な面にプラスして、お嬢さま女房達に欠けているプロ意識批判や和泉式部や清少納言への批判、そして「かういと埋もれ木を折り入れたる心ばせ」という内気な自己分析や生きることの鬱屈という私的な面を併せ持つ、不思議な日記でござった。千年以上読み継がれてきた『源氏物語』、特に卒業最後の単位取得の試験で私を大いに悩ましたことなど、この日記当時の紫式部には知るよしもござらんことでせう。2016/03/07
-
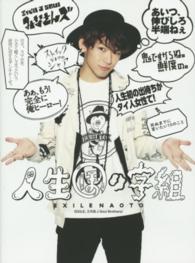
- 和書
- 人生ほの字組
-

- 電子書籍
- 海外赴任のために必要なこと - 駐在員…