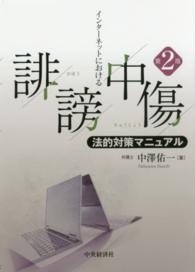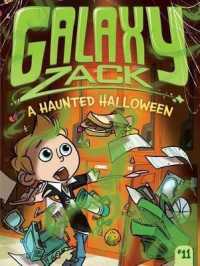内容説明
宮本武蔵は実在の人物だが、その生涯を伝える史料はほとんどない。吉川英治の『宮本武蔵』によって、求道者としての武蔵のイメージが定着し、沢庵やお通をめぐる人間ドラマも多くの読者の共感を呼んだ。吉川が描いた武蔵は、戦前、戦中、戦後と日本人の庶民感情の中でさまざまに読みとられてきており、その後の作家たちが吉川作品への挑戦として描いた武蔵の像を追うことで、武蔵は日本人にとって何だったのかを考察する。
目次
第1部 吉川英治『宮本武蔵』論
第2部 作家たちの武蔵(勝者から敗者へ―坂口安吾『青春論』・村上元三『佐々木小次郎』;武蔵ぎらい―山本周五郎『よじょう』;救済としての武蔵―小山勝清『それからの武蔵』;贖罪の完成―五味康祐『二人の武蔵』;技能者の欲念―司馬遼太郎『真説宮本武蔵』『宮本武蔵(日本剣客伝の内)』
“実”を呑む“虚”―柴田錬三郎『決闘者宮本武蔵』
武蔵奪回―光瀬龍『秘伝・宮本武蔵』『新宮本武蔵』
遠景としての武蔵―早乙女貢『武蔵を斬る』
吉岡家の立場―澤田ふじ子『黒染の剣』
老いと痛まぬ心と―藤沢周平「二天の窟(宮本武蔵)」 ほか)
終章 武蔵論の余白に、或いは、何故『バガボンド』なのか
著者等紹介
縄田一男[ナワタカズオ]
1958年、東京生まれ。専修大学大学院文学研究科博士課程修了。文芸評論家。『時代小説の読みどころ』(日本経済新聞社/増補版・角川文庫)で中村星湖文学賞を受賞。『捕物帳の系譜』(新潮社)で大衆文学研究賞を受賞。アンソロジーの編者としても活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。