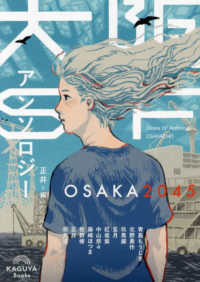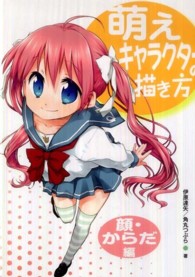内容説明
織田信長の家臣・木村忠範は本能寺の変後の戦いで、自らが造った安土城を枕に壮絶な討ち死にを遂げた。遺された嫡男の藤九郎は家族を養うため、肥後半国の領主となった加藤清正のもとに仕官を願い出る。父が残した城取りの秘伝書と己の才知を駆使し、清正の無理な命令に応え続ける藤九郎―。戦乱の世に翻弄されながらも、次から次に持ち上がる難題に立ち向かう藤九郎は、日本一の城を築くことができるのか。実力派歴史作家が描く、日本一の城を造った男の物語。
著者等紹介
伊東潤[イトウジュン]
1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海―加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』(PHP研究所)で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞、『国を蹴った男』(講談社)で第34回吉川英治文学新人賞、『巨鯨の海』(光文社)で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞、『峠越え』(講談社)で第20回中山義秀文学賞、『義烈千秋天狗党西へ』(新潮社)で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
とん大西
133
人にドラマあり…です。本能寺の変を境に運命が反転した木村藤九郎。父次郎左衛門は自ら普請した安土城で討死。雌伏の時を経て仕えた先は加藤清正。天の配剤か運命か。この出会いがなければ後の熊本城が築かれることはなかったかと思うと感慨深い。亡父が残した秘伝書、藤九郎の柔軟な思考と人当たり、そして清正との水魚の交わり。技官として真摯に城造りまちづくりに取り組む藤九郎。try&error、その青春の息吹は微笑ましい限り。いつの時代も仕事は人を成長させる。それにしても伊東さん、熱い男を描かせたら流石の流石(^.^)2021/04/17
Willie the Wildcat
97
職人としての「技」と、ヒトとしての「義」が、父からの遺産。困難の中、私心なく大義を念頭に、愚直に絡まった紐を解く。築城はあくまで手段であり、信頼を勝ち得ていく過程が、コトの本質という気がする。故の表題。父の”枠”を超える決意の瞬間、そして迎えた藤十郎の死が、職人・ヒトとしての成長のためのもれなく転機。主人公が成し遂げた仕事で印象的なのは、蔚山城。その運命は、正に父の教えの根底に繋がる。文字通り最後となった現場での勝鬨。皆からの感謝を込めた祝砲。グッとくる。清正も、カッコよすぎるなぁ。2021/02/11
のぶ
96
面白いプロジェクト物の歴史小説だった。戦国ロマンですね。主人公は木村藤九郎という本能寺の変後に自ら築いた安土城を枕に討ち死にした織田信長の家臣、木村忠範の息子。その人物の一代記の物語。肥後への赴任を前に加藤清正の家臣として召し抱えられる。タイトルから分かる通り、熊本城を築城する話だがそれが展開するのは後半で、前半では領内の治水工事や築城や、秀吉の朝鮮出兵で清正とともに朝鮮半島に渡り、頭角を現す。帰国後、熊本城の築城が始まる。城は完成するのか?仕事や研究熱心の男の活躍に胸を打たれた作品だった。2020/11/11
at-sushi@進め進め魂ごと
91
城取の父が遺した秘伝を継ぎ、加藤清正に仕えることとなった木村藤九郎(架空)が、増え続けるタスク、相次ぐリスケ、人力や資材不足という困難を、熱意と知恵と人望で乗り超え、ついに史上最強、やりすぎ城とも言われる熊本城を築くまでを描く成長譚。熊本城と清正公が大好きな熊本県民的には理想の上司として描かれる清正像がたまらん。近所の地名が頻出するのも嬉しく、熊本県民必読w 熊本地震からはや5年。今月末には復旧した大天守の観覧が再開されますので、感染対策のうえで是非お越しください。(←ステマ)2021/04/03
さつき
76
加藤清正に仕えた城取り(築城家)木村藤九郎が主人公。熊本城の美しい石垣がどう作られたか興味がありましたが、そこに至るまでの藤九郎、そしてその主君清正の道のりの険しさに圧倒されました。朝鮮出兵の辛苦は聞き知っても見知らぬ異国で築城する厳しさまでは想像していなかった。どのような意図で、何を想定して巨大城郭が作られたか。興味は尽きないし、その差配をした職人達の人生にも思いを馳せたくなります。2023/04/25
-

- 和書
- 渋滞学 新潮選書