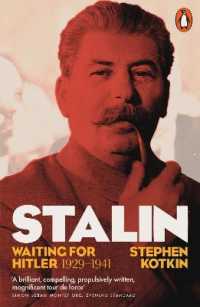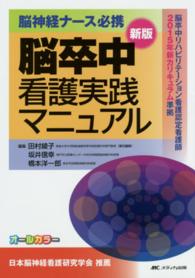内容説明
シックイ、茶、急須、ウダツの原型を考えつつ、著者は蘇州や杭州を歩く。紹興では作家魯迅を思う。名作「故郷」の舞台である。少年時代の魯迅の英雄、幼友達の〓(るん)土の孫が、当時の魯迅記念館の責任者だった。筆者はうれしくて飛び上がる。旅の終わりは寧波。船に乗って港を走ると、回りは中国伝統の帆船、ジャンクだらけだった。ジャンクもまた、筆者のあこがれだった。
目次
蘇州の壁
伍子胥の門
宝帯橋
盤門
呉と呉
呉音と呉服
亡命と錦帯橋
「うだつ」と樋
西湖の風〔ほか〕
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの蛩音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
264
中国・江南の地、蘇州、杭州、紹興、寧波を巡る思索の旅。そして、その途次で、これらの地に関わる人々を俎上に乗せてゆく。江南紀行ではあるのだが、基軸となるのはあくまでも日本であり、かつてこの地を訪れた空海であり、道元である。一方の中国側の登場人物として、ページを割かれているのは魯迅くらいであろうか。また、時に司馬の思念はこの地から逸脱したりもするのだが、それ故にこそ独特の紀行と成り得たのである。今(当時)の中国の景を見て、往時(時には遥かに遣唐使の時代。また時には宋の時代)を想像するのだが、そのよすがと⇒2025/12/28
chantal(シャンタール)
76
【司馬遼太郎の八月 真夏の街道まつり2018】蘇州、杭州、紹興、寧波と言う中国江南の地を巡る旅。司馬さんが旅したのは80年代前半、私が初めて中国を訪れたのは91年、その頃に近い雰囲気でとても懐かしかった。また中国の歴史の復習も出来た気がする。「項羽と劉邦」や「空海の風景」も読んでいたので、どの話題にもすんなりと入れたし、司馬さんの中国に対する理解の深さにも脱帽。浙江省に行くと、私もどことなく日本を思い出させる時があり、司馬さんが見た風景を私も追体験したような、そんな気になってとても楽しかった。2018/08/21
kawa
38
現在の中国の政治の中心地である華北の文明とは異質な後進地域と見なされていた江南地域、蘇州・杭州・紹興・寧波を巡る旅。古代から江戸までの日本にとって、この地域は文明の巨大な灯台として、遣隋使、遣唐使、日明、日清貿易等の窓口の役割を担っていたという。中国に対する地理感も曖昧であまり関心もなかったのだが、スペインの街並みを感じさせるという蘇州や杭州は、俄然、訪ねたい街リストにランクイン。中国茶のヨーロッパへの輸出の流れや、日本の東北地方の砂金が中国からペルシャへの流れたなどの話も興味深い。2020/08/25
AICHAN
33
図書館本。長江河口の江南地方は日本と縁が深い。まず、弥生人の多くがここから渡来した。遣唐使・遣明使はこの江南の地を目指した。江南地方は驚くほど九州に近い。このコースは両国において当然のように取られた航路なのだ。そういう知識だけがあって、しかし中国のことは何もわからず、だからこの「江南のみち」は長年読みたかった。日本人のルーツを探るヒントを掴みたいからだ。しかし、読み進むうちにそんなことを忘れた。司馬さんの博識による洞察によって、日本の多くのモノやコトが中国由来だと知らされ、自分の無知を恥じた。2016/05/31
kawa
28
(再読)「項羽と劉邦」読了の勢いで、不得手な中国ものを再読。「江南」とは長江(揚子江)下流部の南方にある江蘇省南部から浙江省北部にかけての地域を指し、古代、黄河流域の中心地からは蛮地として蔑まれていた。浙江省蘇州、杭州、紹興、寧波(ニンポー)、会稽山等を訪ねるが日本との関わりが深い中で、遣隋・遣唐使の最澄・空海・栄西らが上陸したであろう寧波・三江口での考察が劇的。2023/05/29
-

- 洋書電子書籍
- パンデミックのためのデジタル・イノベー…
-
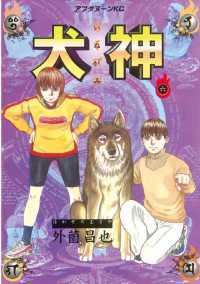
- 電子書籍
- 犬神(6)