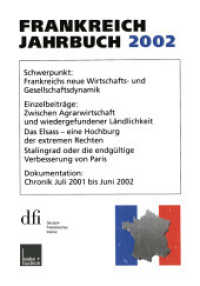出版社内容情報
食卓上に置かれた食器、その奥が気になる。
ディープなインド台所紀行!
南アジア各地の食器・調理器具の輸入販売者にして日本屈指のインド料理マニアのアジアハンターが、インドの端から端まで、さまざまな台所をめぐる――。
料理のみならず、食器や調理器具、調理工程に着目し、歴史や文化、社会問題などにも触れながら、これまであまり取り上げられてこなかった「食」の内側を覗き、さらにディープな食世界へと誘う、インド台所紀行!
本書で紹介するのは、北は夏でも朝晩寒いカシミールから、南は呼吸するだけで汗の出るタミルの最南部まで、巨大な冷蔵庫を6台も抱える大富豪から、わずかな身の回り品しか持っていない路上生活者までの、さまざまな調理現場である。(…)一戸一戸の立場や地位、地域は異にしながらも、全体として共通するインド像が浮かび上がってきた」
――「はじめに」より
◎カラー写真多数
内容説明
南アジア各地の食器・調理器具の輸入販売者にして日本屈指のインド料理マニアのアジアハンターが、インドの端から端まで、さまざまな台所をめぐる―。料理のみならず、食器や調理器具、調理工程に着目し、歴史や文化、社会問題などにも触れながら、これまであまり取り上げられてこなかった「食」の内側を覗き、さらにディープな食世界へと誘う、インド台所紀行!カラー写真多数。
目次
北インド(カシミールの宴席料理ワーズワーンの世界 シュリーナガル1;旧市街の奥の堅牢な館 シュリーナガル2 ほか)
南インド(白米と雑穀のはざまで チェンナイ1;異国で食べる昭和レトロメシ チェンナイ2 ほか)
東インド(「正しい」台所とは何か コルカタ1;ビハーリー・マン・イン・コルカタ コルカタ2 ほか)
西インド(世界最大のスラム街 ムンバイ1;憧憬と追憶のボンベイ ムンバイ2 ほか)
著者等紹介
小林真樹[コバヤシマサキ]
東京都出身。インド・ネパールの食器、調理器具を輸入販売している有限会社アジアハンター代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
Toshi
ばんだねいっぺい
アリーマ
Sakie
-

- 電子書籍
- 宮廷をクビになった植物魔導師はスローラ…
-
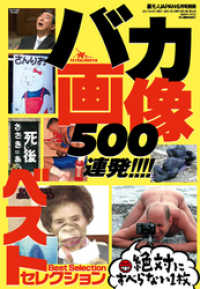
- 電子書籍
- バカ画像500連発!! ベストセレクシ…