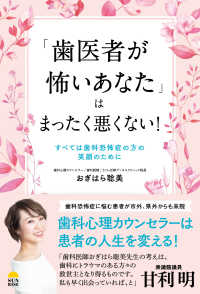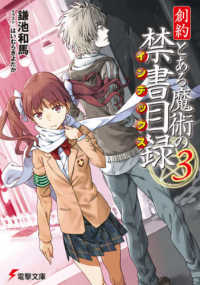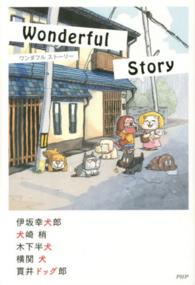内容説明
「自分が学校から脱落するのではなく、自分から学校にさよならする」と決めた14歳の少女夏実。「ほかの子がちゃんと行ける学校へ、行けないような子に育ててしまった」と自らを責める母の史子。肉親、隣人・教師たちはそれぞれの立場から、この母娘を見守る。無機質なシステムと化した学校をめぐる問題を、現代を生きるすべての人々に関わるものとしてとらえた社会派小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
雛
5
1987年朝日新聞の連載小説。当時の連載小説は今よりエンタメ性の少ない、硬いものだったんだな。当時買った単行本、シミだらけの「黄色い紙」になっているのを、我慢して再読。 中学生の夏実も母の史子もとても真面目だ。 30年以上経って、今の中学校の教師と生徒はどういう状況なんだろうとふと思う。 決して関係ないわけではない、大事な孫たちが何年か後には行くことになるのだから。2021/10/25
ウメ
3
中学のころ登校拒否児だった私にかるーく「行きたくなければ行かなくていいさー」と言ってくれた父。学校という小さな社会が全てで、不安で潰されそうな心がその一言でどんなに救われたか。今だから分かる親の有り難み。私の自慢の父。2021/11/24
にゃおん♪
2
何度目かの再読 ウォークinチャコールグレイを読んだら、必ずその後に読んでいる…かも。私が持ってる干刈あがたの本はこの2冊だけだもんなー。他のも読んでみるか。図書館行ったらあるかな。 朝日新聞の連載が始まったのが1987年5月(リアルタイムで読んでました ^^;) 25年以上前の作品なのに問いかけられてることは今もかわらないような気がする。いつ読んでも心にひっかかるフレーズがあるよなぁ。2014/06/15
かりん
1
4:《どれが正しいかは自分で決める。》単行本にて。新聞連載時に奥山民枝さんが挿絵を描いていたということで「どんな話だろう」と気になった。いじめで学校に行けなくなった夏実とその母の思いは、どれもわかるというか、どれが正しいかは自分で決めるしかないというか。メモ→夏実は自分が、柏木史子は柏木賢治の遺児をちゃんと教育しています、という〈生きた証拠〉として送り出されているような気がした/親って、子供が可愛くていい子で、他人に対して親であることを恥じないでいられるうちは愛しているけど、そうじゃなくなると憎むのよねF2021/09/29
ma
1
システムから逸脱して究極の自由を手に入れても、結局、得るものも失うものも半々。正しいかどうか、幸福かどうかを決められるのは自分だけっていう極めて凡庸な結論・・・数年後再読したときにどう感じるのか楽しみ。2014/04/01