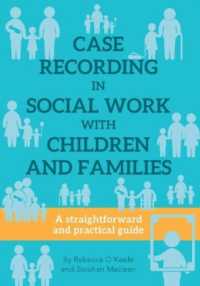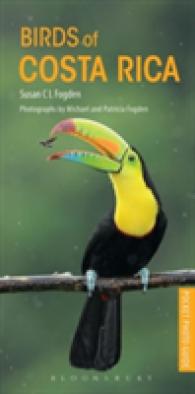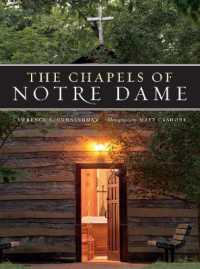目次
近江散歩(近江の人;寝物語の里;伊吹のもぐさ;彦根へ;金阿弥;御家中;浅井長政の記;塗料をぬった伊吹山;姉川の岸;近江衆;国友鍛冶;安土城趾と琵琶湖;ケケス;浜の真砂)
奈良散歩(歌・絵・多武峯;二月堂界隅;五重塔;阿修羅;雑華の飾り;光耀の仏;異国のひとびと;雑司町界隅;修二会;東大寺椿;過去帳;兜率天)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
k5
65
実家で法事をするというので関西へ。すっかり新幹線のおともとなった『街道をゆく』ですが、あえて実家のある奈良を選んでみたところ、なんだか見たことのないような静謐できらびやかな世界が展開していました。東大寺にはゆかりのある学校に通っていたもので、修二会のみならず人物名まで出てくる固有名詞に馴染みが深いのですが、こんな世界だったかしら?東大阪在住の司馬遼が奈良ホテルにわざわざ宿泊しているし、これは異世界の奈良かと思いました。2022/07/03
kawa
45
(再読)近江路&奈良路編。今週、奈良(大安寺展)、ついでに近江路&関ヶ原戦跡巡り予定で、主に近江路の情報再確認のために手に取る。情報取得はそれなりだが、安土城跡を訪れたおりの、子供の頃に見た風景とのあまりの悪化、落差ぶりの記述が印象的。琵琶湖の埋め立て等による環境悪化を批判した司馬先生、今の湖はどうなのだろうか?須田画伯が戦中、新薬師寺に寄宿していたという事実も興味深い。追っかけをして見ようかな、画伯のオリジナリティあふれる生涯。そうそう、華厳経をめぐる大安寺との因縁も知れてラッキー。2022/06/13
kawa
40
近江(湖東)・奈良と素材としては重量級。近江は寝物語の里、不破関資料館、国友鉄砲資料館、安土城跡、近江八幡水郷辺りをテイクノート。奈良は東大寺の根本経典「華厳経」、と二月堂の「お水取り(修二会)」に関する部分が読みどころ。短文ながら須田画伯の画家としての来歴の項も面白くも興味深い。同時に眺めた「週刊・街道をゆく02,16」のグラフ誌も、本編購読の一助に、誌上旅気分を高めに大変グッド!2020/10/02
キムチ
24
再読。長政とお市は血液で日本史に参加したのだ」には参った。長政は尾張に攻め入り 「屈した思いの家康」と異なり 其処の兵を「地侍ども」と呼び捨てる。自身が持つプライドは後世でしか判定できないわけだが。 奈良散歩・・といっても寺や僧侶のエピソードが溢れる。東大寺も興福寺も「外形は変わらず、時間だけが・・」は いわば、晴天の星座を眺めている風情なのだろう。登場する人物は老成した感覚の人物が多い。明治以前から脈々と文化を伝えてきたのは「歴史連鎖して 歳をとることのない僧」だったのだろうか。2013/12/06
Book & Travel
23
関西帰省中に奈良を訪れるにあたり、司馬遼太郎記念館にて購入。東大寺の修二会を代表とする千年以上変わらないものを続けていくということ、またそれを取り巻く人々の営みが興味深く、廃仏毀釈で大きく衰退した明治維新期の(旧)興福寺と対照的な印象を受けた。また今回訪れた興福寺の阿修羅像、薬師寺の再建などのエピソードもあってとても楽しめた。近江の方は数回しか訪れたことはないが、新幹線の車窓の風景で一番好きなのは古い家並の集落が続くこの地域。かつては歴史の中心となった地域だけに話も豊富で、いずれゆっくり訪れてみたい。2015/08/14
-

- 電子書籍
- 美少女学園 西川茜 Part.98 美…