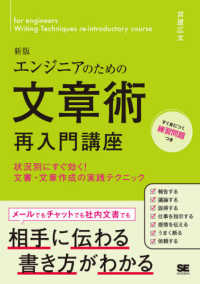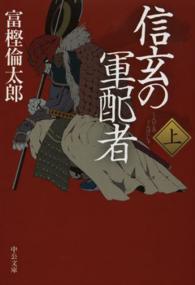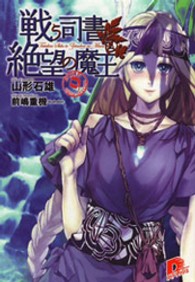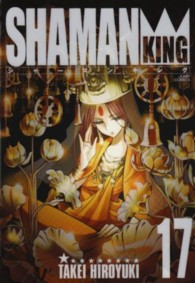内容説明
脱ゆとり、学力重視へと舵を切った教育政策。この間、受験対策を掲げ、圧倒的に存在感を増した学習塾と、方向転換にとまどい、指導力不足に悩む学校の間でさまよう子どもたちに、いま、ほんとうに何が必要なのか。
目次
第1章 脱「ゆとり」、そして歓迎「学力」へ
第2章 「鬼っ子」・学習塾の台頭
第3章 学習塾を急成長させた「合格」というニーズ
第4章 学習塾成長の皮肉な“応援団”
第5章 揺らぐ学校
第6章 学校に入り込む学習塾
第7章 文部科学省解体へ
終章 学校をどうするのか
著者等紹介
前屋毅[マエヤツヨシ]
1954年、鹿児島県生まれ。法政大学卒業。週刊誌記者を経て、現在はフリージャーナリスト(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
hori_syu
1
学校が目指すべき道はどこにあるのか。学習塾が『学力』を『テストの点数』だけのものとして子供たちに指導する。学習塾はこれでいいかもしれないが、学校はこれではいけない。学校とは人格形成の場であり、人としてのいわゆる“教養”や“倫理観”を学ぶ場である。学校の存在意義が薄れている現在。本書は学習塾と学校と官庁を客観的に分析し貴重な視点を学ばせてくれる本です。学校関係者の方にも是非お勧めしたい一冊でした。2010/06/05
Shun Kozaki
0
学力低下論・格差社会論の原因のひとつ=塾産業 という朧げな図式を頭に描いていたので、手にとってみた。当然一般向けの本だから、さくさく解りよいが、どうにもビジネスライクな話が多いのが鼻につく。 また、具体性にもかけているような気はする。提言がない。 学校現場の弱みが個への対応、学習塾の強みがまたそれであり、学力偏重主義、ゆとり教育すら塾産業のターゲットになるわけだけれども、やはり影響は公教育体制の上意下達的性格と現場の教師のおかれる環境のむつかしさにあるんだと思う。2015/01/12
numainu
0
評価D2006/11/11
ホセ
0
[図]共存の道もある2009/03/05
-
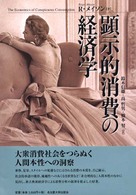
- 和書
- 顕示的消費の経済学