出版社内容情報
マーラーの真の新しさや面白さは,世紀末ウィーンの文化史全体に目を向けて初めて明らかになる.著者はクリムトやフロイトらの活動をも視野に入れ,彼らの夢と現実のありようを描き,現代のマーラー受容の意味を問う.
内容説明
マーラーの作品の真の新しさや面白さは、世紀末ウィーンの文化史全体に目を広げて初めて明らかになる。著者は同時代人クリムト、O.ワーグナー、フロイト、V.アードラーらの活動をも視野に入れ、彼らの夢と現実のありようを描きだす。また現在、彼の音楽のどのような側面が注目され、それが現代文化のいかなる状況を表現しているのかを問う。
目次
第1部 同時代者の中のマーラー(花形指揮者の憂鬱―一九世紀の歌劇場の状況の中で;芸術による社会革命の夢―マーラーと学生運動;意識下の世界の探索―マーラーとフロイト;綜合芸術の館―マーラーと分離派;指揮者マーラーの挑戦―マーラーのベートーヴェン受容 ほか)
第2部 現代人の中のマーラー(マーラーとポストモダニズム―芸術とキッチュのはざま;音楽の「論理」の解体―音楽の空間性;ワルター神話を超えて―『第四』演奏史の分析)
著者等紹介
渡辺裕[ワタナベヒロシ]
1953年千葉県に生まれる。東京大学文学部(美学芸術学)卒業。同大学院修了。東京大学大学院人文社会系研究科教授。音楽学専攻。著書に『聴衆の誕生』(春秋社、サントリー学芸賞受賞)などがある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
16
マーラー入門には最適の一冊なのではないか。世紀末ウィーンの都市背景と現代までのマーラー受容を紐解きながら、作曲家の特性に迫っていく。その特徴は①音楽・文学・絵画・演劇などを一体化させるワーグナー的総合芸術家という意識②近代化が進むウィーンの騒然とした風景を内在化した、騒がしいポリフォニー③分断された大衆性と高尚性に橋をかけるためのギリギリの通俗性④時間軸に沿ったストーリーがない代わりに空間配置性が強調されるサウンドデザイン、といったあたりか。最後の章の各演奏のテンポ比較は自分の耳でも確認したいところ。2017/04/09
おとん707
12
初出は1989年だから趣味としてのハイエンドオーディオが盛んだった時期で、そんな環境に乗る形でマーラーの大規模な交響曲が一気に注目を得た時代。だから現代のようにマーラーがベートーヴェンやブラームスのようにレパートリーとして定着した時代の評論ではない。という事で作曲家マーラーを生んだ当時のウィーンの社会的背景から丁寧に説き起こしている。なので楽曲の解説は後半に押しやられた形だが、マーラーを古典の枠組みから解き放った演奏と古典の枠組みの中で捉えた演奏の対比と考察など興味のある内容だ。因みにワルターは後者だ。2024/10/16
げに
1
マーラー関連本①。 マーラーを取り囲んでいた時代思潮が手堅く整理されている良質な入門書。 もはやマーラーに慣れっこの現在から見るとあまり真新しい記述があるわけではないが、現在初版刊行時(1990年)の、ポストモダン思潮と結びついたマーラー・ルネサンスの空気を伝える資料として読むほうが面白い。2016/08/15
みかん
1
世紀末ウィーンの文化的空気を概観できる良書。後半のマーラー演奏解釈史はさすが渡辺先生といったところか。2015/07/13
にかの
1
世紀末ウィーンの文化についてはカール・ショースキーの著作を読んでいましたがマーラーについてあまり詳しくは述べられていなかった所がありました。本書はそれを補完する目的で購入したのですが予想以上に面白く、マーラーその人や作品の面白さなども知ることができました。マーラーの作品についてはリッカルド・シャイーのマーラー全集における演奏が名作との誉れ高いので値段ははりますが是非とも聞いてみたいと思います。2012/05/27
-

- 電子書籍
- 推しとの同居が尊すぎます!【タテヨミ】…
-

- 電子書籍
- 救世主の生き残り 第22話【タテスク】…
-
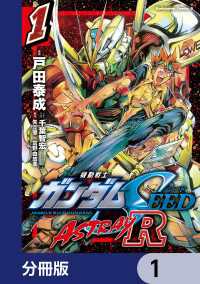
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY…
-
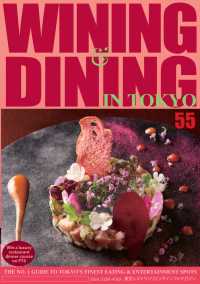
- 電子書籍
- WINING & DINING in …
-
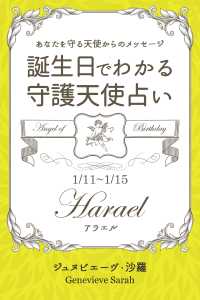
- 電子書籍
- 1月11日~1月15日生まれ あなたを…




