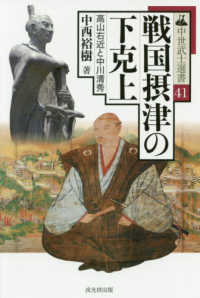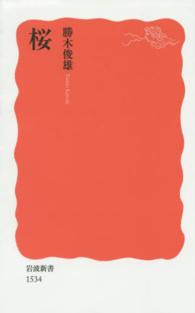出版社内容情報
電子の端末が膨大なコンテンツから美しい「ページ」を開く今、本とは? 書店・図書館ほか本の仕事人、練達の書き手・読み手の鋭いアンテナ37人が応える。内田樹、上野千鶴子、出久根達郎、長尾真、原研哉、松岡正剛ほか。
内容説明
グーテンベルク革命から五世紀。電子の端末が膨大なコンテンツから美しい「ページ」を開くこの時代、あなたにとって「本」とはいったい何か。それはいかに変貌するのか。書店・古書店・図書館・取次・装丁・編集、そして練達の書き手・読み手の位置から、鋭いアンテナの持ち主たちが応える―本の過去と未来を俯瞰する三七のエッセイ。
目次
電子書籍時代(吉野朔実)
本の棲み分け(池内了)
発展する国の見分け方(池上彰)
歩き続けるための読書(石川直樹)
本を還すための砂漠(今福龍太)
本屋をめざす若者へ(岩楯幸雄)
書物という伝統工芸品(上野千鶴子)
活字中毒患者は電子書籍で本を読むか?(内田樹)
生きられた(自然としての)「本」(岡崎乾二郎)
本を読む。ゆっくり読む。(長田弘)〔ほか〕
著者等紹介
池澤夏樹[イケザワナツキ]
1945年北海道生まれ。作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
131
題名にある通り、これから本の存在はどうなっていくのかあるいは読書はどのようなことになっていくのか、本にまつわることを本について一家言を持つ識者が小論を書いていて、それを池澤さんが編纂したものです。長田弘さんの「本を読む。ゆっくり読む。」というようなものにあこがれてしまうのですがまだその境地に至ってはいません。福原義春さんの「紙の本に囲まれて」というような感じにも憧れます。2015/12/04
mitei
77
電子書籍がいよいよ始まるというときに時の読書家?が自分の本との付き合いを振り返ってみたような内容だった。これからも紙の本は滅ぶことはないとの結論が多かった。自分もどんどん紙の本で読書をしていきたい。2011/05/04
kaizen@名古屋de朝活読書会
73
編者が名前を出した本。星と風のバグダット。聖書。シェイクスピア全集。グレートギャッツビー。艶婦伝。弘法大師和讃。 電子書籍を改良する側の人間として読んだ。上野千鶴子が「伝統工芸品」として本が残るという。本の値段が高くなければ伝統工芸品でも可。電子書籍は便利にならないと本を凌駕しない。便利にする方法は特許になっているかもしれない。 焦点がぼけている意見があるように感じた。電子書籍が本に取って代わるのは、レコードがCDに変わるよりも遥かに難しいかも。岩波新書百一覧掲載http://bit.ly/10CJ7MZ2013/03/22
つちのこ
37
この本、図書館で拾ってきたリサイクル本だが、発行年は2010年。新書のウリは新しい情報の吸収にあると思うが、さすがに15年も前になると時代遅れは否めない。2010年は電子書籍元年であり、iPadが発売された年。本書の書き手が論じているのは、電子書籍の存在意義や将来性についてが中心で、それぞれの言い分が面白い。出久根達郎は古本屋店主だけあって、コレクションの対象とならない電子書籍は流行しないと言い切り、成毛眞は書庫を愛する自分にとって、本の電子化は困ると書く。上野千鶴子は諦めているのか、いずれ書物は⇒2025/01/03
ユウユウ
37
本が積み重なることに喜びを覚える本好きがいる限り、紙の本はなくならない。たしか成毛さんが書かれていたと思います。まったく同感です。そして本が紙の本として築き上げてきた世界のことを思うと、電子版の儚さは恐ろしくさえ思うのです。今までに消えてきたデジタルの記録メディアの数々(フロッピーとかMOってわかる方いますか?)を思えば、紙の媒体に勝るものは無いと思う。そして今日も私は積ん読するのです。2019/04/11