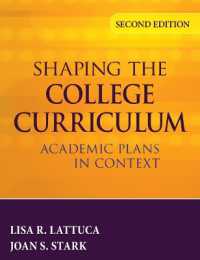内容説明
戦国大名への華麗なる転身!細川氏・三好氏・荒木村重など群雄ひしめく戦乱の中で、政局を左右した国人たち。信長・秀吉の登場で巻き起こる、過酷な生存戦略の実態を解き明かす。
目次
第1部 右近と清秀のルーツを求めて(戦国の幕開けと国人たち;守護と守護代の狭間で;京兆家の争いと国人)
第2部 高山飛騨守の登場(覇権は細川から三好へ;高山ダリヨの誕生;和田惟政と池田勝正)
第3部 摂津の大名に成り上がる(荒木村重離反の余波;織田信長の摂津侵攻と右近・清秀;豊臣秀吉と戦国摂津の終焉)
著者等紹介
中西裕樹[ナカニシユウキ]
1972年生まれ。立命館大学文学部史学科日本史学専攻卒業。現在、高槻市教育委員会文化財課主幹(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
48
地元ゆかりの大名「高山右近」と「中川清秀」に焦点を当て、戦国時代の摂津北部の様子を書き記した一冊。著者は高槻市教育委員会文化財課主幹の中西裕樹氏。右近・清秀二人のルーツ、周囲を取り巻く時代背景、二人や一族のその後など。他にも、三好長慶、荒木村重、和田惟政、池田氏一族、伊丹氏など多くの武将が登場。摂津国は上郡、下郡、欠郡、北郡の4群からなり、特に上郡と下郡の争いが歴史的背景にあることを知りました。芥川城、郡山の戦い、かくれキリシタンの里、忍頂寺など、近所の名所・寺院も登場、ぜひ一度行きたいと思いました。2023/10/22
きみたけ
41
いま住んでいる高槻・茨木を中心に活躍した高山右近と中川清秀の生涯にスポットを当てた一冊。とても勉強になりました。芥川山城、富田宿場、郡山合戦、安威、中河原、忍頂寺など、普段買い物などで通りすぎる地名がたくさん出てきて少し興奮しました。高槻は戦国におけるキリシタンの聖地となった経緯も理解できました。高山右近の足跡を訪ねるのも良いかなと思いました。2021/08/11
ほうすう
12
副題に高山右近と中川清秀とある割にはその両名の記述はさほど多くはない。戦国時代の摂津全体を描いたもので、応仁以降から織田豊臣による支配までの過程を描いてくれたものとして個人的には嬉しかった。ただ分かりやすくはない。戦国期の摂津というと最も下克上が激しく複雑な変遷を見せた地域でしょう。だから書くのに苦労するというのも分からなくはないのだが、それを加味しても時系列が前後したり唐突に城の話を詳しく延々と書いてたり思ったことをそのまま書き散らしているのではというところもあったりと、読みやすいかというとなんとも。2019/11/15
MUNEKAZ
10
副題に高山右近と中川清秀とあるが、2人がメインとなるのは、かなり後半になってから。むしろ一介の土豪に過ぎなかった高山氏と中川氏が、摂津を代表する勢力にまで成長した過程を追っている。細川→三好→織田・豊臣と機内の支配者が目まぐるしく変わる中で、それと連動して守護代→国衆・池田氏→その家臣・荒木村重→右近・清秀ら土豪たちと下克上が為されていくのが面白い。また高山右近については、彼を通して畿内でのキリスト教受容も描かれており、これも興味深かった。決して読みやすい内容ではないが、いろいろと勉強になる。2019/09/02
六点
8
応仁の乱以降、「混乱の大地」と呼ぶしか無いように見える、摂津国の戦国時代。淀川沿いの「上郡」大阪湾岸の「下郡」山間部の「北郡」大阪湾岸南部の「欠郡」、それぞれに蟠踞する国人がどのように蠢き、離合集散し、最期は歴史の波の中に埋没していくかまでを詳しく描かれている。本書の「主人公」である高山右近や中川清秀、荒木村重、それ以前の国内の旗頭達は、まるで暴れ神輿に担がれ、周囲の動向で放り出されぬ様に必死であったのだなと思う。歴史上の人物でありながら摂津方言で会話してたらと想像すると、喜劇的な悲劇に思えた。2020/04/05