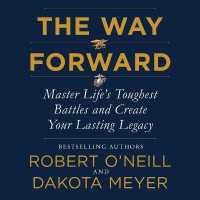内容説明
勤めていた工場の廃業によって、小関さんが50年間誇りにしてきた肩書「旋盤工・作家」が消えた。仕事を守りつつ、生活と現実から実感する喜びと悲しみを作品として書くことは、人生にどんな意味をもつのか。いま、自分と社会について深く考えるために文章を書こうとする人々に表現することの精神と方法を、自らの体験をもとに語る。
目次
1 働きながら書く
2 わたしの読書術
3 走り書きのメモから教えられる
4 編集者との出会い
5 小説の取材、ノンフィクションの取材
6 町工場巡礼の旅をする
7 旋盤工・作家のナカグロ
著者等紹介
小関智弘[コセキトモヒロ]
1933年東京に生まれる。都立大附属工業高校卒業後、51年から大田区内の町工場で働きつつ作家活動をつづける。2002年、つとめ先の工場閉鎖により51年間の旋盤工生活に終止符をうった
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
80
この本の題名を見て購入した人は、肩透かしを喰わされた気がするかもしれません。文章教室とあるので間違えやすいと思われます。内容的には旋盤工・作家という肩書を持つ著者が自分の読書経験や本を書くについての様々な自分の経験を書き留めてきたものです。私はそれなりに楽しめました。2015/09/23
佐島楓@入院中
41
題名から想像していたものと違い、プロレタリアートとしての小説をテーマにしたエッセイであった。著者が生きてこられた時代が強く感じられたし、労働をきちんと書いてこなかった日本の小説というくだりにも考えさせられた。2015/09/03
薄い月明かり
2
働いている時間は文章修業の時間を単に削ぐものではなく、労働を通して感性を深め、豊かな表現を生むものだと信じたい。 「どうしても今書きたい」というモチーフ (動機) が立ち現れてくれば、形式や書き方にこだわらず、まず手を動かしてみようと思う。それを実現するには、懸命に働きながら書くしかない。 言葉を発しない人びとの「素朴」こそを、変化する時代の証言者として描くことを目標に掲げ、読み、書き、語り合う楽しみを持ちながら続けていきたい。 叶うならば、それを分かち合える人をひとりでも持ち得ることができれば嬉しい。2023/05/28
たらお(専門書用アカウント)
2
文章の書き方に関しては特に解説はありません。 読むこと、書くことで得られる体験の素晴らしさを説いている一冊です。 書く趣味を持っている方には是非読んでいただきたい。 著者の経験から語られる仕事論やその仕事だからこそ見えてくる世界、発見にも学ばせていただきました。 「まずは書いてみろ、あとは手が教えてくれる」 「どんな仕事であれ人は労働を通じてさまざまな人生を学ぶことができる。そこで学んで深めた感性が、豊かな表現を生むのである」 ←本書で何より伝えたいことはこれでしょう。ずしりと胸に響き、受け止めました。2023/07/17
かたつむり
2
ハウツー本ではなかったが、それを期待しなければ著者の人生の中の文学の位置付けについて書かれていて読み物として面白かった。2011/07/31
-

- 和書
- 社会思想史ノート 〈続〉