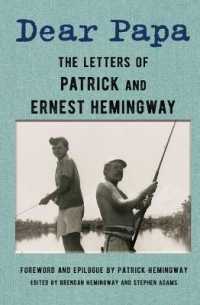出版社内容情報
死とは何かを問うことは,同時に,生とは何かを問うことであり,人間とは何かを考えることでもある.ソクラテスやイエス・キリストの死生観・霊魂観をさぐり,モンテーニュやパスカル,さらにわれわれの同時代人たるサルトルなど,ヨーロッパのすぐれた知性が,死をどのように受けとめ思索したのかを,わかりやすく描いた哲学的エッセイ.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぼけみあん@ARIA6人娘さんが好き
9
実存哲学者である著者の死生観ではなく、ソクラテスと新約聖書、モンテーニュ、パスカル、サルトルの死生観が分かりやすくまとめたテキスト。ただ、ソクラテスの死生観に関しては、プラトンのパイドンを下にした場合ソクラテスの名を以て語られたプラトン自身の死生観である可能性が高いのだけど、哲学の専門家なのに、その辺はどうでもよいのかなと多少気になった。また、新約聖書の死生観についても残念ながら鵜呑みにはできそうにない。まあ、軽く読んで、西洋の代表的思想家の死生観を勉強するにはよい本だと思う。2015/04/29
那由田 忠
8
キリスト教の中で「魂」がどのように入ってきたか(ユダヤ教では死ぬと塵に戻る)が書かれていないかと、昔手に入れて半分しか読んでいなかったこの本を読み通してみた。魂の話はソクラテスにしか登場しなかった。とりあえず、この非ギリシア的な概念が、ローマ帝国の国教化する中でキリスト教の中に入ったと考えておく。私も年をとって死への恐怖を感じなくなったので、この本で何か得るものがあったわけではない。しかし、サルトルが、死から生を照射するようなハイデッガーに対して、死は一つの偶然的な事実と割り切った点に、大いに賛同する。2014/04/29
coaf
6
ソクラテス、イエス、モンテーニュ、パスカル、サルトルの紹介。著者の思索はなかったので残念。2013/07/02
式
5
ソクラテスの章は、『パイドン』の議論を丁寧に追う。キリスト教の章は、ギリシア語の観点で、ソクラテス的なプシュケーの退潮、プネウマとサルクスの対立、新約はプネウマの書という辺りは良かったが、イエスの生涯を追って結局何が言いたいのかわからない。モンテーニュの章は、死に馴れ親しむ術、自殺について、自然順応への展開。パスカルの章は、深淵の誤解、気ばらし、二つの本能、死刑囚の比喩。サルトルの章は、対自は死とともに消失して即自の内に呑み込まれる、死は全ての可能性の無化、生者たちの餌食、死は可能性ではなく偶然的な事実。2023/01/10
nekonon
3
平易な表現で語られる様々な死生観の本。この中だと私は圧倒的にモンテーニュの考え方が好きだなあ。「エセー」いつか読む。 平易な表現とは言ったものの、あ、わかりやすい、と思って油断して読んでると、突然話が難しくなって思考の階段を転がり落ちることしばしば。特にサルトルの「即自」と「対自」の部分はさっぱり意味がわからなかった・・・。哲学は文学より数学の証明問題に近い気がする、と、こういう文章を読むたびに思うのです。むつかしー。2013/07/01
-

- 和書
- 立体製図 - 技能訓練