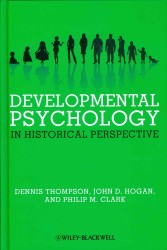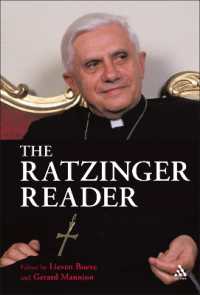出版社内容情報
シンボルを生み出し、これを操作することこそ人間と動物を区別するものであり、哲学に関心を抱くものは、その基礎をなすシンボルとその意味を認識しなければならない--。アメリカにおける記号論の礎を築き、これを芸術の哲学に発展させた古典的名著。シンボル機能の結実である言語、音楽、美術、神話、祭儀などを具体的に論じる。
内容説明
シンボルを生み出し、これを操作することこそ人間と動物を区別するものであり、哲学に関心を抱くものは、その基礎をなすシンボルとその意味を認識しなければならない―。アメリカにおける記号論の礎を築き、これを芸術の哲学に発展させた古典的名著。シンボル機能の結実である言語、音楽、美術、神話、祭祇などについて具体的に詳説する。
目次
第1章 新しい基調
第2章 シンボル変換
第3章 サインとシンボルの論理
第4章 論述的形式と現示的形式
第5章 言語
第6章 死生・シンボル、聖体祭儀の根元
第7章 死生のシンボル、神話の根元
第8章 音楽における意義について
第9章 芸術的趣意の発生
第10章 意味の織物
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
8
シンボルとその作用。 お互いに映し合う鏡の球が網目に無数に連なる空間。 私たちはシンボルとして、世界を捉え、世界に己を編み込んでいく。 シンボルは一方で言語を産み、一方に音楽を生む。 自分自身を捉えることもシンボル化なのだろう。 音楽は非言語的なものであり、言語のような意味の共有は稀である。 軍楽の太鼓なども含めた労働歌、動きに規律を生むものなどを別にすれば、言葉の意味などなきに等しい。 感動というのは、打ち震えるもので、音の波であり、芸術である音楽に、私たちは共鳴する。 2022/07/30
パン
2
終始興奮しました。ちょうどヴィトゲンシュタインの論理哲学論考を読んだ(勉強中)あとなのと、言語学的視点でシンボルについて考えたかった故に刺さりまくりました。2022/02/11
ゆきじん
1
最初の方は参考になった。途中から一読では理解しづらくなり、後半は何を言ってたんだか判らずに終わった。何回か読めば良いかもしれない。2022/12/01