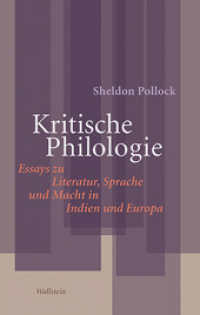出版社内容情報
明治政府による不当な差別を目の当たりに見,骨身にしみて育った伊波普猷(1876-1947)が,沖縄の歴史,言語,民俗を探究した,沖縄学樹立の記念碑的作品.『おもろさうし』とともに沖縄を知るための必読の古典.
内容説明
薩摩藩による支配に続く明治政府による沖縄と沖縄人に対する不当な差別を目の当たりに見、骨身にしみて育った「沖縄学の父」伊波普猷。本書は、彼が沖縄の歴史・言語・民俗を探究した、沖縄学樹立の記念碑的作品であり、歌謡集『おもろさうし』とともに沖縄を知るための必読の古典である。
目次
琉球人の祖先に就いて
琉球史の趨勢
沖縄人の最大欠点
進化論より見たる沖縄の廃藩置県
土塊石片録
浦添考
島尻といえる名称
阿麻和利考
琉球に於ける倭寇の史料
琉球文にて記せる最後の金石文〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ノコギリマン
31
言語学としての琉球史って感じでした。阿麻和利についてのところなんか、すごい面白かった。P音考、ここいらへんから言われはじめたやつなんですね。面白かったです。オススメ。2015/07/09
サイバーパンツ
10
言語学から見る琉球史。中でも、P音考が面白い。P(パ)→F(ファ)→H(ハ)という日本語の音韻の変化を沖縄を物証として証明するというものだが、これアイヌ語でも似たような指摘がなされているし、世界レベルで通じる論かと思う。P音を多用したPPAPが、あれだけ世界中でブームになってるんだし。2017/02/08
Happy Like a Honeybee
8
沖縄民俗学の研究に。 興味深かったのは、沖縄の地名にアイヌ語が使われいる点である。東京や埼玉でもアイヌ語の地名だけが残存しており、その形跡が伺える。遠く離れた沖縄でもアイヌ人が存在していたのか…。東をアガリ西をイリと読む。アイヌ人も日本人も東に向かって進んだ事を意味する。 鎌倉時代の日琉貿易。日本の神話と共通点が多い琉球神話。 柳田国男との交流は眉唾である。2017/10/24
MIYA
5
氏の墓標を訪れたこともあって、この「古琉球」を拙いながらも読了。「浦添考」は自分が住む町の歴史を知る上でも興味深かった。曲亭馬琴の著した「椿説弓張月」の考察も掲載されており、同作品を読んだ身としては見識がさらに深まる思いだった。また、伊波氏の論文だけでなく、外間守善氏による伊波氏の生涯の解説も面白い。氏の沖縄への思いがひしひしと伝わってくるようだった。「歴史を軽視する者は歴史に罰せられる」とは池上彰氏の言葉だが、歴史を知れば知るほどその言葉の重みが分かる気がする。2014/04/26
ymazda1
3
薩摩による琉球支配の苛烈さみたいな話に対する客観的な文献史料の不在っぽさが気になって読んでみた本・・・相応に頁を割かれてる薩摩以前の八重山征伐の話とかを読んでると、久米村人>琉球人>宮古人>八重山人 といった、薩摩を抜きに存在していたっぽい支配被支配の多重構造がなんとなく気になってくるというか・・・そして、宮古島の水にまつわる悲話も、今も延々と続く内閣府の地下ダム工事からも、決して誇張ではないと思えるわけで・・・その辺が、いろいろと都合のよい言説作りの土壌になってたりしてるんかもなって思った。。。