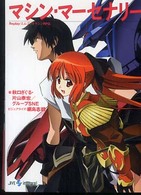出版社内容情報
経済学の歴史に「ケインズ革命」と呼ばれる一大転機を画した書。新古典派理論の特殊性と決別し、雇用と有効需要、利子率と流動性とを組み合わせた「一般理論」を構築。現代経済学の出発点にして、今なお必読の古典の待望の新訳。
内容説明
経済学の歴史に「ケインズ革命」と呼ばれる一大転機を画した書。資本主義の抱える大量失業と不安定な経済循環への処方箋として、雇用と有効需要、利子率と流動性とを組み合わせた「一般理論」を構想。現代経済学の出発点にして、今なお必読の古典。待望の新訳。
目次
第1篇 序論(一般理論;古典派経済学の公準;有効需要の原理)
第2篇 定義と概念(単位の選定;産出量と雇用の決定因としての期待;所得、貯蓄および投資の定義;使用費用について;貯蓄と投資の意味―続論)
第3篇 消費性向(消費性向(一)―客観的要因
消費性向(二)―主観的要因
限界消費性向と乗数)
第4篇 投資誘因(資本の限界効率;長期期待の状態;利子率の一般理論;古典派の利子率理論;マーシャル『経済学原理』、リカード『政治経済学原理』、その他に見られる利子率について;流動性への心理的誘因と営業的誘因;資本の性質に関するくさぐさの考察;利子と貨幣の本質的特性;雇用の一般理論―再論)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
58
古典経済学のアダムスミスの経済原論,マルクス経済学の資本論,近代経済学のケインズの一般理論,現代経済学のサミュエルソンの経済学の4冊が、ある時代まで経済学部の教科書として引用。数学の考え方である限界理論を経済学に適用しようとした試みは、その後のコンピュータの発展とともに、実用的になっている。仮説はあくまでも仮説であり、現実と誤解しないようにすることが大切である。現地現物の中には、従来の実際の物やお金の流れ岳でなく、ネットワークを通じた口座の振替も範囲内であるため、架空の話と現実の話を混同しないことが大切。2011/04/23
静かな生活
10
気合いでなんとか読み通す。単純な「経済を回せば社会が回る」公式に対して「いやしかし…」という注釈みたいな但し書きをひたすら書き記していくという構造。マルクス主義みたいなダイナミズムがあるわけでもないし資本主義を全肯定しているわけでもないという、なんとも言い難いバランス感覚。あと、数式は大体読み飛ばしました。すまないケインズ2022/01/11
柏もち
10
書き方は分かりやすいのに内容が表面的にしか入ってこない。定義付けの話が長い分、そもそも自分が様々な語の定義をよく理解していないことを突きつけられ、ミクロ経済とマクロ経済で学んだ理論と現実経済の動きとを上手く結びつけて考えられていないことが浮き彫りになった。とりあえず自分の課題は分かった。本書は消費性向の分析・資本の限界効率の定義・利子率の理論の三点を中心に展開される。 十七章の利子率の話がとくに興味深かった。2016/05/16
Francis
10
あまりにも有名な経済学の古典。とは言え、多分経済学部出身者でも読んだ人は10人に一人ぐらいかも。上巻では有効需要、消費性向、投資要因など、ケインズ経済学の基礎的用語について語られる。注目すべきは彼が経済成長が進んでこれ以上成長が望めない準定常状態について語っていることで、ケインズが資本主義の未来についても深く考察していたことがうかがえる。やはりケインズは天才だ。2014/06/11
ヨンデル
9
昔読んだ本です、整理のため登録しています。2024/07/14