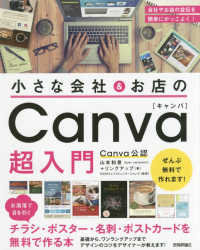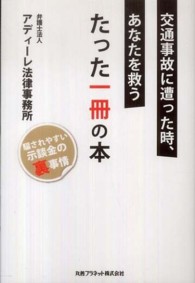出版社内容情報
明治一九(一八八六)年は,維新以降,最大の不況の年だったといわれる.この年,『朝野新聞』に連載された「府下貧民の真況」は,東京の下層社会を記録するルポルタージュの先駆となった.このルポをはじめ,明治年間に書かれた東京の下層社会に関する生活記録の中から,幸徳秋水「東京の木賃宿」,横山源之助「貧民の正月」等十四篇.
内容説明
明治19(1886)年は、維新以降、最悪の不況の年だったといわれる。この年『朝野新聞』に連載された「府下貧民の真況」は、東京の下層社会を記録したルポルタージュの先駆であった。このルポをはじめ、明治年間に書かれた東京の下層社会に関する生活記録の中から、幸徳秋水「東京の木賃宿」、横山源之助「貧民の正月」等14篇を収録した。
目次
1 異質さへの関心(府下貧民の真況;窮民彙聞;貧天地饑寒窟探検記抄;東京府下貧民の状況)
2 固有の生活世界(東京の貧民;昨今の貧民窟)
3 社会批判の介在(世田ヶ谷の繿縷市;下層社会の新現象共同長屋;東京の木賃宿;下谷区万年町貧民窟の状態)
4 下層社会の変容(貧民の正月;共同長屋探見記;貧街十五年間の移動;下級労働社会の一大矛盾)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月世界旅行したい
11
これに近い状況やここに出てくるようなタイプの人とかかわったこともあるのでひとごとではない。2015/04/05
壱萬参仟縁
10
横山源之助(『日本の下層社会』)氏も寄稿されている(3本)。貧民窟。現代はシェアハウスということでかろうじて貧困をやり過ごそうとしている若者、非正規の人がいる。それ以外はネットカフェとか。いろんな職業があったようだ。按摩、納豆売り、鼻緒職、櫛職、煙草行商、紙屑買い、日雇い、三味線弾き、米搗き、屑拾い、硝子屑買い、左官、人力挽き、僧侶、井戸掘(鋼職)、傘直し、賃仕事、髢(かもじ)職、・・・全部で、63種も書いている(41頁)。なのになんで貧しいか。東京各区でも貧民がいたのだ。芝区西応寺の大妻長屋(82頁)。2013/04/14
刳森伸一
6
著者不詳の「府下貧民の真況」や桜田文吾の「貧天地餓寒窟探検記」のような最初期の貧民窟ルポルタージュから、ジャーナリストであり社会問題研究家の横山源之助が執筆した記事まで、明治時代の下層社会やそこで生きる人々、そして彼ら、彼女らに向けられた視線を縦断的に知ることができるように資料を集めた文集。物見遊山的に貧民窟を闊歩する段階から貧困を社会問題として捉えていく過程が見えて興味深い。2020/12/11
うぃっくす
4
うーん、興味深い本だった。明治時代の有名な貧民窟は、上野の下谷万年町、芝新網、四ツ谷鮫ヶ橋だったらしい。時が経つと郊外になってくけど。主な職業は日雇い人夫か紙屑拾い、妻は内職。子沢山で木賃宿か共同長屋で生活してるけどお金がなく病気と飢えに常に悩まされてた、と。けどそんな中でも節約して子供に正月いい服着せてあげたりとか長屋の困ってる人のためにみんなでお金だしあったりとかのあったかさもあり。乞食の勢力図みたいなの興味深かったな。今の東京からはほんと思いもよらないよね。300年くらい前の暮らしに想いを馳せたわ。2019/12/14
徳島の迷人
3
明治時代東京貧困街の風俗についての報道を集めた本。日払い、一人に一畳程度の広さの安宿(木賃宿)で住む者が多く、宿を逆にしたドヤはこの時代からあったよう。生活は江戸時代のようだが衣服道具は全てボロ、残飯を食べ、臓物を食べ、紙屑(その他ゴミ)拾いや人力車や日雇い作業で命を繋いでいく。子供らは乞食や泥棒になり、学校には行けない。病気になっても医療費は出せず、葬式は質素な土葬。実は日換算では木賃宿は割は良くないが、手持ちが無いから入居する人も多い。現代のネットカフェ難民のようで、やはり全体的に共通する点は多い。2022/12/23
-

- 洋書
- TRYSTERO