内容説明
女性解放運動の先駆者として名高い山川菊栄(1890‐1980)とその母青山千世(1857‐1947)の、女性二代にわたる自叙伝。「明治」初期から「昭和」の敗戦後に至る激動期を舞台に、水戸から東京に出た母の青春、著者の学校時代、山川均との結婚生活、活動家として生きた日常が、多くの同時代人の肖像を織り込んで活写される。
目次
ははのころ(明治前半)(水戸から東京へ;荒れ野原の東京 ほか)
少女のころ(明治後半)(お月さまいくつ;桜ふぶきの庭 ほか)
大正にはいってから(『青鞜』と真新婦人会;焼き打ちと米ツキバッタ ほか)
昭和にはいってから(思い出の元旦;錦のみ旗と逆賊 ほか)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
14
菊枝の母親が東京に出てきた明治5年。明治維新で焼かれることはなんとか免れたものの「三百諸侯と旗本八万騎という寄生階級を中心に栄えていた消費都市江戸は、武家制度が亡びると同時に荒れはてて」いた。旧都江戸が東京へと変貌していくなか、津田塾に通う菊枝は創始者梅子のことを「英語だけ教えてくれればいいのに、うるさいババァだなあ。。」 (^^;) と思いつつ、おんなとしての生き方を模索していく。https://bookmeter.com/reviews/881090682020/03/14
ミーサ
6
朝井まかてさんの「恋歌」から思い出して、これと「幕末の水戸藩」を借りてきた。これは山川菊栄とその母の事が書かれていて、母の家系は水戸幕末の武士の家であったので。文明開化したとはいえ、女性が勉学をし独り立ちするなんて考えられない時代に前を見て進んできた女性たちであったことが伺える。戦前までは、貧困や女性問題など、弱者の権利を守る運動として社会主義や共産主義に光を見いだしていたのだと思う。現代の私達はその行き詰まりを目の当たりにしているのだが…。2017/08/03
シンドバッド
5
かなが多く読みづらいものの、内容は、大変、興味深い。山川菊栄は、積ん読であったが、他の著作も、読む意欲が、出ました。2014/11/10
る
4
山川菊栄の戦後までの自叙伝。同時代を生きたたくさんの人(伊藤野枝、大杉栄カップルなど)が出てきてそれだけでも面白いが、たまに挟まれる菊枝さんのニヒルな一言が最高で人間的な魅力を感じた。彼女の言説も全く古くない。特に女性公論で伊藤野枝、与謝野晶子とやりあった廃娼論争と母性保護論争について、現代の人は正直山川菊栄の意見が一番違和感なく受け止めることができるのでは。2023/12/25
あすか
4
この自叙伝を書いた山川菊栄さんという方は明治から昭和にかけて活躍した社会主義思想家かつ女性解放運動家だそうです。日本において、かつては社会主義運動と女性解放運動が密接に関わっていたことが意外でした。女性解放運動家というと、いわゆる「女を捨てた」タイプをイメージしてしまっていたけれど、この方の場合女性のしなやかさや柔和さと聡明さや強さを兼ね備えていて好印象でした。平易な語り口で端々にユーモアがあり読んでいて面白かった。2016/08/31
-
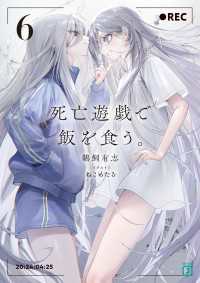
- 電子書籍
- 死亡遊戯で飯を食う。6【電子特典付き】…
-
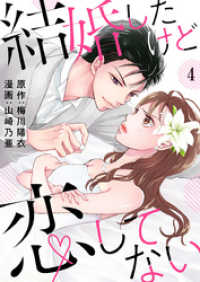
- 電子書籍
- 結婚したけど恋してない 4巻 A-LI…







