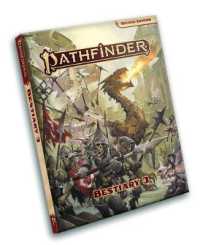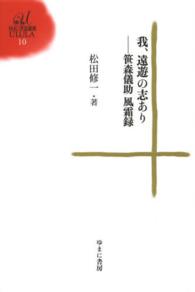出版社内容情報
学問一途の若い学者ミシェルは,新婚の旅の途中喀血し,その回復期にはじめて自己の肉体に目を向け,生の歓びを知った.爾来彼の心は一変した.従来の学問・道徳に対する懐疑と官能的生のあくなき享受.次第に彼は「背徳者」と化してゆく.これは,既成のモラルに安住しえなくなった魂の,痛ましい苦悶の告白である.一九○二年作.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
318
タイトル(原題も"L'immoraliste"だから、ほぼ直訳か)から、ジイドとピカレスクな悪漢小説とは意外な組み合わせだと思ったが、どうやらここでいう「背徳」は、神を信じないこと=神への背徳のことであるようだ。手記の語り手であるミシェルは通常の意味においては、背徳からは遠いからである。現代的な観点からすれば(とりわけ日本の精神風土にあっては)、何が問題であるのかはわかりにくいのだが、主題を「神からの自立をはかろうとする青年の物語」として読むならば、20世紀の初頭においての本書の新しさは首肯できそうだ。2017/09/30
mii22.
54
私自身が漠然と思い描いていた背徳者とは少し違っていた。私が感じたのは煩悩と倦怠と悲哀。旅先で重病から回復したミシェルは、はじめて生きることへの歓びを見出だすが、自由を追い求めてゆくことはしだいに背徳者となることだった。己のなかで沸き起こる欲望に苦悩するミシェルはとても人間くさく感じた。あざやかな対照を成していると解説にある『狭き門』も読まなければ。2017/06/10
パトラッシュ
49
100年以上前のフランスと21世紀の今日では自由や道徳の考え方が違いすぎる。どこかの研究者がミシェルのような生き方を選択しても、ネットで話題にもされない。文明からの脱出とか自然への帰還など、テロやパンデミックの恐怖にさらされる現代では無意味だ。何よりミシェルは単独で行動し、妻以外の他人を巻き込んでいないのは暴走気味の個人主義としか受け取れない。むしろ優秀な数学者でありながら「産業革命は人類に災厄をもたらす」と主張して全米各地で爆弾テロを繰り広げた「ユナボマー」ことセオドア・カジンスキーとの類似点を感じる。2020/11/04
きょちょ
31
ガーディアン1,000冊から。 1部は「静」、2部は「動」か。 主人公の場合の背徳は、「心変わり」ということだろうか? 「心変わり」は背徳でも何でもないはずだが、主人公には全く共感できない。 むしろ脇役のメナルクの方が一本筋が通っていて、作者は「対比」させたかったのか? しかしそれも良くわからない。 感じるものはなかった・・・。 ★2019/06/21
wiki
24
『狭き門』と対をなすとされる本。両書を合わせ読む事で、著者が提起した内容はじっくりと思索できると思う。本書は自制的な生き方を捨て、自らの意志と感覚に忠実に行動した結果の不幸である。『狭き門』は宗教的自制が起因の不幸であったから、対照的だ。宗教の奴隷になれば不幸だ。しかし一方で自身の感覚を至上とする一種のエゴイズムも、不幸はまぬかれない。本書が描いた通りだ。思想信条の奴隷にはなってはならない。一方で、一定の自制を促す思想信条はやはり必要だ。そう結論付く。とすれば次は、いかなる思想を持つべきなのか、だと思う。2021/09/04