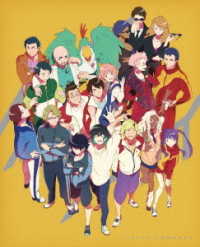内容説明
願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月の頃―。山家集、聞書集、残集、御裳濯河歌合、宮河歌合ほか、現在知られている西行の和歌のすべて約2300首を集成。脚注のほか、詳細な補注・校訂一覧を付し、広く日本の詩歌に関心のある読者にとって読みやすいのみならず、専門家による研究にも資するべく編纂された決定版。
目次
山家集
聞書集
残業
御裳濯河歌合
宮河歌合
拾遺
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
74
西行については、辻邦夫『西行花伝』など各種の本で親しんできた。先月、書店の岩波文庫のコーナーで本書が目についた。 「山家集」など個々のものはそれなりに手にしてきたが、この際、全歌集にチャレンジするのも酔狂かなと。やや無謀かもしれないが、折々親しみたくなる歌人…謎の人なのである。2022/08/08
1.3manen
24
自然と共にある。そして、自然を歌に詠みこむ。現代人がなかなか感性面で彼に引けを取る気がする。1030「古里は 見し世にも似ず あせにけり いづち昔の 人行きにけん」(165頁)。古里は見た世の中にも似ていない。荒れてしまった。昔見知っていた人はどこに行ってしまったのだろうか(脚注をも参照)。うーん。地域再生を。論文とは、菩提心論の要分(278頁)。227「木曾人は 海の碇を 沈めかねて 死出の山にも 入りにけるかな」(291頁)。木曾人は木曽義仲のこと(脚注)。山育ちへの皮肉。縁語と掛詞も巧み。2014/03/01
双海(ふたみ)
18
約2300首。すごい・・・。2014/05/13
syaori
17
山家集は再読です。御裳濯河歌合と宮河歌合が読みたくて手にとりました。前者は俊成が、後者は定家が判詞を書いています。この判詞を依頼された当時、定家は25~26歳。恐らくようやく御子左家の跡継ぎとして認められてきた頃で、前年に「二見浦百首」を詠んでいます。既に歌人としての名声もあった西行から自歌合の判詞を頼まれた定家は悩みに悩んで、完成に2年をかけました。読んでいて、俊成に対し確かに定家は一番一番、細部まで気を使って書いているなと感じました。俊成や定家の歌に対する美学も窺うことができるので興味のある方はぜひ。2016/01/06
shou
11
2300首、さすがにこれだけあると多方面な魅力もわかってくるけども、やはり「願わくば~」や「鴫立つ沢の秋の夕暮れ」のような季節の歌が素直に好きだなあ。自選歌合せの判定評価が興味深い。「門ごとに立つる小松にかざられて宿てふ宿に春は来にけり」「梢打つ雨にしをれて散る花の惜しき心を何にたとへん」「ながめつる朝の雨の庭の面に花の雪敷く春の夕暮」 2015/09/03
-

- 電子書籍
- バラッド×オペラ【タテスク】 Chap…