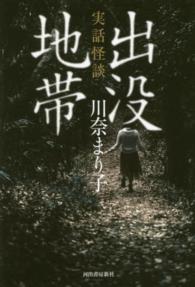出版社内容情報
自助組織に端を発し、国家や行政、企業と異なる役割を持つ協同組合。JA(農協)を軸にそのルーツを探り、現代的な意味を再考する。
内容説明
私たちの身近にある、古くて新しい自主自律の組織、「協同組合」。その理念と実践が評価され、ユネスコの無形文化遺産にも登録された。JA(農協)を軸に、歴史的ルーツと可能性を探る。日本農業新聞の好評連載を、大幅に補筆して書籍化。
目次
第1章 協働組合ことはじめ(世界初の協同組合―大原幽学の挑戦と挫折;信用組合の礎を築く―二宮尊徳と報徳社の思想と実践;かたちなす産業組合―近代化の進展のなかでの農協前史;小作人から自作農へ―敗戦と農地改革;農協の成立―DHQの意向と創成期の難航;共済への道―賀川豊彦らがめざした命を支えるしくみ)
第2章 海外の源流と今に学ぶ(欧州・東アジア各地の農村協同組合―その誕生と成長;ルポ二一世紀の協同組合―脈々とつづく創始の精神)
第3章 これからの協同組合―よき未来のために(国際的な協同組合運動と日本の総合農協―ICA九五年原則とJA綱領;協同組合の組織―出資、参画、利用の一体性;協同組合の事業とJAがめざす姿―総合事業が支える営農とくらし)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
36
大原幽学の講義は討論を重視した(6頁)。現代のアクティブラーニングになるのか? 二宮尊徳が「五常講」を発案し、資金の貸付や預金の受け入れをする金融の協同組合、信用組合の原型(14-15頁)。横井時敬(ときよし)・高橋昌の『信用組合論』(31頁~)。柳田国男と岡田良一郎の論争(36頁~)。農村信用組合は、19C半ばにドイツ南西部で誕生。ライファイゼンによる、農村経済の自立と回復めざして発足(148頁)。自分たちさえ良ければいい、という考えではなく、組合員が住み協同組合が存在する地域社会を、 2018/01/18
土橋俊寛
0
スーパーと生協、生保と共済組合の違いは?ひと言で言えば協同組合は「助け合い」のための組織。その目的を果たすために購入・販売・共済などの事業を行なう。営利目的でないのが特徴。構成員は組合員なのだが、組合員だけでなく組合が存在する地域をより良くするというミッションも持つ。本書ではそんな協同組合の源流を詳しく解説する。日本では大原幽学や二宮尊徳にまで遡れるとのこと。 近年、協同組合の持つ「一般の企業にはない耐久力や回復力」が注目されているという(204頁)。協同組合について知るために本書はうってつけだと思う。2021/01/24