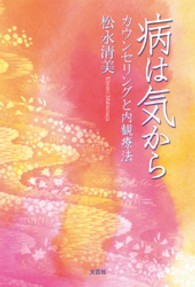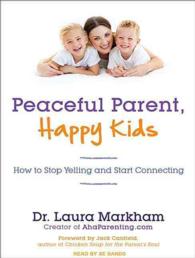出版社内容情報
いま,人類学はどのような可能性をもつのか.本書は民族,文化,地域などの基本概念を再検討し,人類学の記述や方法を根底から問い直す.研究者のみならず,多元化する世界の中で「異文化」を考える読者にも必読の書.
内容説明
21世紀の人類学の可能性とは。半世紀にわたるアフリカ、日本、ヨーロッパのフィールドワークをふまえ、言語、民族、地域、歴史、文化、他者認識などの人類学の基本概念を根底的に問い、人類学の理論と方法を再検討する。研究者だけでなく、多元化する世界のなかで異文化理解を考える読者にも必読の書。
目次
序 人類学的認識論のために―「私」と人類のあいだ
第1章 ヒト中心主義を問い直す
第2章 民族と政治社会―西アフリカの事例を中心に
第3章 「地域」とは何か―その動態研究への試論
第4章 「しるす」ことの諸形式
第5章 イスラーム音文化の地域的展開
第6章 肖像と固有名詞―歴史表象としての図像と言語における意味機能と指示機能
第7章 歴史の語りにおける時間と空間の表象
第8章 エギゾティスム再考―ピエール・ロティの「永遠の郷愁」
第9章 黄色いニッポン・ムスメの悲劇―『蝶々夫人』が提起するもの
第10章 旅人の目がとらえるもの―柳田国男「清光館哀史」を問い直す
著者等紹介
川田順造[カワダジュンゾウ]
1934年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科文化人類学分科卒業、同大学大学院社会学研究科博士課程修了。パリ第5大学でアフリカ研究では日本人として初めて博士号を受ける。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授、広島市立大学国際学部教授を経て、現在、神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科教授、神奈川大学日本常民文化研究所所員。主な著書に『曠野から―アフリカで考える』(筑摩書房、第22回日本エッセイストクラブ賞)『無文字社会の歴史』(岩波書店、第8回渋沢敬三賞)『サバンナの音の世界』(東芝EMI、1984年度文化庁芸術祭レコード部門優秀賞)『声』(筑摩書房、第26回歴程賞)『口頭伝承論』(河出書房新社、第46回毎日出版文化賞)など多数。1991年フランス学士院よりフランス語圏大勲章、1994年フランス政府より文化功労章、2001年紫綬褒章、2002年小泉文夫音楽賞(第13回)を受ける
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。