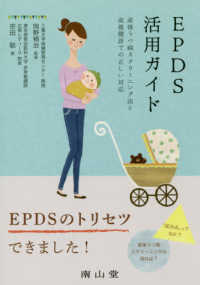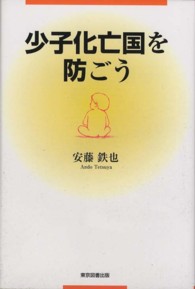出版社内容情報
命題論理・述語論理や様相論理など形式論理の基礎を学んだあと、ゲーデル不完全性定理を通して「計算」の意味を理解する。さらに計算モデルの典型であるラムダ計算について学習し、論理と計算をつなぐ「仕組み」を理解する。
内容説明
論理と計算の概念は、いまでは計算機科学の基盤となっている。本書は、命題論理や述語論理、そして様相論理など形式論理の基礎を学んだあと、ゲーデル不完全性定理を通して「計算」の意味を理解する。さらに計算モデルの典型であるλ計算について学習し、論理と計算の関係だけでなく、両者をつなぐ「仕組み」を理解する。
目次
1 集合と関係(集合;関係)
2 命題論理と述語論理(命題論理;一階述語論理;高階述語論理とその部分体系)
3 様相論理と直観主義論理(命題様相論理;多重様相論理;時相論理;命題直感主義論理)
4 計算可能性(チューリング機械;帰納的関数;不完全性定理;プレスバーガ算術;述語論理の決定不能性と決定可能な部分体系)
5 λ計算(λ項;簡約;型付きλ計算)
著者等紹介
萩谷昌己[ハギヤマサミ]
1957年生まれ。1980年東京大学理学部情報科学科卒。東京大学大学院情報理工学研究科教授。理学博士。専門は、計算機科学
西崎真也[ニシザキシンヤ]
1967年生まれ。1994年京都大学大学院理学研究科博士課程修了。東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授。理学博士。専門は、計算機科学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1
野矢先生の論理学を読み終わった後、高階述語論理が知りたいからと言って買った気がするが、その時は手に負えず数年間積読だった本。とりあえず一通り目は通した。「情報科学における論理」と構成が似ているが、§4のTuring機械の話はこちらのみ。論理とのつながりがわかる。肝心の高階述語論理はあまり紙面が割かれていない。代わりに様相・直感主義論理に結構詳しい。ゲーデルの不完全性定理をTuring機械の停止問題として解くのは中々な発想だと思う。全体的に、詳しいところとそうでないところがある気がする。2024/04/07
嘉村 崇宏
1
論理と計算の概要と両者をつなぐことを意識して記述された本。論理と計算の心を知るには良いが、これで論理と計算を身につけることは少々難しい様に思える。入門書としては良いかもしれない。2015/03/27