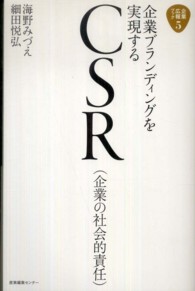出版社内容情報
明治政府が公費一四万五千円をかけ全力投球で迎賓館を建設したのは,外国との条約改正を何としても有利に展開したいためだった.文明開化を支えたものは何か,井上馨,伊藤博文ら指導部の人間像とともに生きいき描く.
目次
江戸から東京へ
開化を支えるもの
鹿鳴館と条約改正
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
扉のこちら側
60
2017年375冊め。1859年代の江戸幕府が結んだ不平等条約(治外法権、関税自主権の欠如)を撤廃させるには、同じテーブルにつく手段を講じなければならなかった。その点を鑑みると、よくは言われない鹿鳴館の時代も必要だったのだろう。一時代で終わった鹿鳴館だが、文明開化は確かに国民に残った。2017/11/02
うんとこしょ
1
鹿鳴館そのものについてというより、鹿鳴館が象徴する明治政府樹立以来の欧化政策を大久保利通、伊藤博文、井上馨といった人物たちの思想を絡めながらの政治史及び社会史といった内容。江戸幕府終焉による江戸の人口低下、銀座大火の後の煉瓦街化再建による日本橋から銀座への商業中心地への移行などの指摘など興味深かった。2015/11/20
rbyawa
1
e197、もともといわゆる社交界の話が目当てで手に取ったものの、語られていたのは明治4年の岩倉使節団とその目指した「不平等条約の改正」であり、頓挫したのちにこの鹿鳴館が建てられ、欧米人の生活スタイルを日本で実践しようとした、ということが語られていたんですが。この後閉鎖された日本が辿った歴史はまあ、確かに言われて見れば軟化と排外の繰り返し、猿真似と呼ばれようとも、外に開こうとした気概くらいは認めてもいいんじゃないかな、と言われていたんですが、日本の鹿鳴館の猿真似ではない進化系も見てみたかった気はするかなぁ。2014/07/16
-

- 洋書
- MA MAMAN