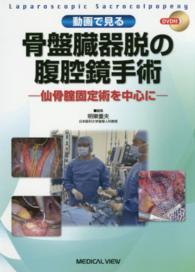内容説明
地域包括ケアは“身の丈”で実践する
東広島の「町のかかりつけ医」が描く、
地域医療の持続可能なかたち
若者人口の減少と高齢化率の上昇、そして医療従事者の不足が深刻化するなか、日本の地域医療はかつてない危機に直面しています。
診療所の閉鎖や救急医療の縮小が相次ぎ、従来の医療サービスを維持することが難しくなる一方で、注目を集めているのが「地域包括ケアシステム」です。医療・介護・福祉が連携し、地域全体で住民の健康と生活を支えるこの仕組みは、今後の地域医療の基盤となる可能性を秘めています。しかし現実には、地域ごとに十分な構築・運用が進まず、医療機関や行政、介護・福祉分野の連携が思うように機能していないのが実情です。加えて、人材・資金・設備といったリソース不足も深刻で、理想と現実の間に大きな隔たりが生じています。限られた条件のなかで、いかに持続可能な仕組みを築くか――――その問いが、いま各地域に突きつけられています。
東広島市で四半世紀にわたり診療所を運営してきた著者は、そうした制約の中で「身の丈に合った地域包括ケアシステム」を実践してきました。診療所をハブに、介護・福祉の多職種との柔軟な連携体制を築き、地域のニーズに応じたコンパクトな医療・介護事業を展開。さらに、地域住民の医療リテラシー向上にも取り組みながら、持続可能なケアの形を模索してきました。
本書では、著者が築き上げた地域包括ケアの実践を、具体的な事例を通して紹介します。医療機関だけでは地域を支えきれない時代に、限られたリソースの中でも実現できる“身の丈”のケアとは何か、その答えを現場の経験から導き出した一冊です。
目次
はじめに
第1章 医療リソースや抱える課題は千差万別
地域ごとに独自に構築する地域包括ケアシステム
地域で異なる医療の課題
住み慣れた地域で自分らしい暮らし
予想を上回る速度で進む少子高齢化
2025年問題と2040年問題
各市区町村の特性に合わせたシステムの構築
医師はハブ的存在であるべき
「治す医療」から「治し、支える医療」へ
「生活の場」で受けられる医療・介護サービス
介護保険制度が必要とされた理由
第2章 町のかかりつけ医が地域包括ケアシステムの“ハブ”となる多職種連携を強化する「小回りの利く仕組みづくり」
「人生100年時代」と増え続ける百寿者(センテナリアン)
平均寿命と健康寿命の差
要になるのはケアマネジャーとかかりつけ医
医師会で立ち上げた訪問看護ステーション
「医療と介護で高齢者の生活を支える」
介護認定審査会の委員として
認知症を認めたくない心理
国に先駆けて認知症に関する研修会を実施
地対協の地域ケア促進専門委員会の委員にも就任
認知症に優しい地域づくりに取り組む東広島市
東広島市における要介護・要支援認定率は低下
東広島地区医師会地域連携室「あざれあ」
「あざれあ」開設は厚生労働省のモデル事業から
体制構築に必要な7つの取り組み
つながりを生み出し、育み、広げていく
骨粗鬆症対策の重要性に気づく
東広島骨粗鬆症地域連携会の誕生
持続可能な地域医療介護を体現する仕組み
第3章 デイサービス、グループホーム、在宅医療、居宅介護支援――
限られたリソースで最大限の医療を届けるための「コンパクトな事業の多角化」
父の夢を代わりにかなえるために医師に
「地域医療」との出会い
在宅ニーズは高まりこそすれ減ることはない
「お年寄りが元気になる姿」に感銘
医療と介護の連携による多様なメリット
受け皿としてのデイサービスの存在感
デイサービスを通しての在宅支援の事例 その1
デイサービスを通しての在宅支援の事例 その2
デイサービスを通しての在宅支援の事例 その3
四半世紀続けた居宅介護支援事業所
新たな取り組みとしてグループホームを
グループホーム「ジューンベリーの家」
「いつもは在宅、時々入院!」は安心のキーワード
第4章 予算をかけずに地域包括ケアシステムをよりよく機能させる
ケアの効率化を図るための「地域住民の医療リテラシー向上」
「パーソン・センタード・ケア」について
「医療リテラシー向上」への具体的な取り組み
私が講演に呼ばれて話すこと
医療提供側も意識を変える必要が
今働いてくれている職員たちを大切にする
朝礼でみんなの気持ちを一つにする
地域連携室「あざれあ」の研修プログラム
医師にとっては診察室が原点
第5章 地域の身の丈に合わせれば
誰一人取りこぼしのない地域包括ケアシステムを実現できる
エンド・オブ・ライフケアの拠点づくり
取りこぼしのない地域医療・介護に向けて
要支援・要介護状態で退院する人たちのケア
「身の丈地域包括ケアシステム」をどう維持していくか
おわりに
-
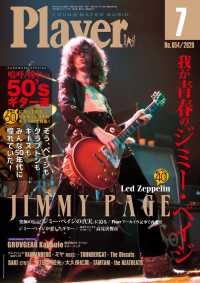
- 電子書籍
- Y.M.M.Player7月号
-
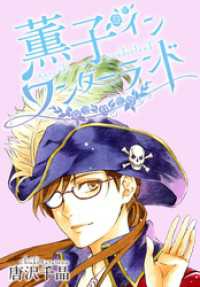
- 電子書籍
- AneLaLa 薫子 イン ワンダーラ…