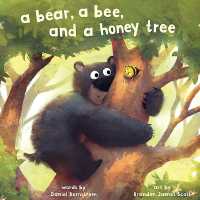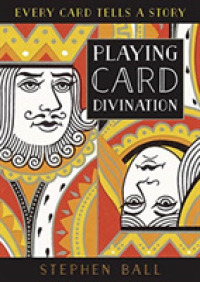内容説明
電子版は本文中の写真をすべてカラー写真に差し替えて掲載。
歩道の隙間、建物の陰、水面……街を歩くとあちこちで雑草に出会う。ひっそりと、ときには堂々と生きている雑草には、どんな「生きぬく力」があるのだろう? 小さな隙間に入り込むスミレ、子孫を残す工夫を幾重にも凝らしたタンポポ、生命力溢れるドクダミ、タネは出来ないがたくましく生き続けるヒガンバナ、ひっそりと冬を越すセイタカアワダチソウ。四季折々の身近な雑草を案内役に個性豊かな植物の生きぬく力を紹介。
◆◇◆目次◆◇◆
はじめに
第1章 春の野や水田で、季節の訪れを告げる植物たち
(1)なぜこんなところに?――スミレ(スミレ科)
春の訪れを告げる花とは?/隙間に咲くスミレ/スミレの名前の由来/巧みな繁殖方法/園芸品種としての特性
(2)1日しか咲かない小さな花――オオイヌノフグリ(オオバコ科)
一面に咲く花の正体/口はばかられる名前の意味とは?/口はばかられる名前をもつ仲間は?/ヒマラヤスギにも松ぼっくり/松ぼっくりの閉じ開きはどうやって?/メシベは、他の株に咲く花の花粉をほしがっているのか?
(3)在来タンポポはほんとうにひよわか?――タンポポ(キク科)
「ライオンの歯」とよばれる理由は?/ネバネバする乳液がからだを守る/セイヨウタンポポの繁殖力/在来種は、ひよわな植物ではない!
(4)水上の小さな驚異――ウキクサ(サトイモ科)
水面に浮いて漂う/驚くべき増殖力/ウキクサが秘めた、命をつなぐ“しくみ”
コラム 気になる名前の植物たち
第2章 夏の野や庭、池で、季節を満喫する植物たち
(1)これもランの仲間――ネジバナ(ラン科)
右にねじれるか、左にねじれるか/ネジバナの学名/新種が発見されて、話題に!/花が、日本では「蝶」、外国では「蛾」に、たとえられるのは?/ラン科の植物たち
(2)夜に眠る葉――カタバミ(カタバミ科)
ハート形の小さな3枚の葉/カタバミの仲間たち/植物は、夜に眠るのか?
(3)植物も汗をかく?――ツユクサ(ツユクサ科)
涼やかな青い花/1日の間にメシベが移動する/夏の暑さに負けない“しくみ”を教えてくれる
(4)匂いで撃退――ヘクソカズラ(アカネ科)
よく見るけれども名を知らない植物/草花も匂いでからだを守る/アカネ科の植物たち
(5)似た名前の植物たち――ヒルガオ(ヒルガオ科)
巻きつく草/ヒルガオの生存戦略とは/ヒルガオの仲間と思われる植物は?
(6)旺盛な繁殖力――ホテイアオイ(ミズアオイ科)
布袋尊のお腹/置かれた場所にふさわしく生きる!
コラム 食べられる「夏の七草」とは?
第3章 夏の野で、暑さに負けない植物たち
(1)巻きひげのすごい能力――ヤブガラシ(ブドウ科)
鳥の脚のような5枚の葉/巻きひげの力と花に秘められた巧みな工夫
(2)群生して育つ――ドクダミ(ドクダミ科)
毒が溜まるか、毒を矯めるか/半夏生か半化粧か/ドクダミの生存戦略/地下茎の威力/“フィトクロム”とは?
(3)日本から世界へ――イタドリ(タデ科)
痛みが取れる?/イギリスでは、嫌われ者の帰化植物/イタドリの生きぬく力/シーボルトがヨーロッパに紹介した意外な植物
(4)したたか? ずるい?――イヌビエ(イネ科)
水田で生きぬいてきた雑草/水田で気配を消しても、“脱粒性”だけは残す!
(5)寄生植物の苦労――ネナシカズラ(ヒルガオ科)
全寄生? 半寄生?/夜をどこで感じるのか/ストリゴラクトンによる「魔女の雑草」の“自殺発芽”
コラム 歌に詠まれる「夏の七草」とは?
第4章 秋の野で、季節を魅せる花を咲かせる植物たち
(1)日本では有用植物、アメリカでは?――クズ(マメ科)
花も根も身近/クズのすごい成長力を支えるのは?/アメリカで、“侵略者”とよばれても!
(2)花だけがポツンと咲く――ヒガンバナ(ヒガンバナ科)
同じ時期、同じ場所で咲く花/「ハミズハナミズ」とは?/土地と光の奪いあいを避けて、生きる!/長くたくましく生きている秘訣とは?/なぜ、お墓に多くあるのか?/競争を避けても、負け組ではない!/なぜ、ヒガンバナにはタネができないのか?/どうして、ヒガンバナの花は、秋の彼岸に咲くか?
(3)嫌われ者も今では――セイタカアワダチソウ(キク科)
帰化植物の代表/大繁茂する生存戦略とは?/“ロゼット”の利点とは?
コラム なぜ、植物の名前はカタカナで書くのか?
第5章 秋の野で、季節を演出する植物たち
(1)生き物の姿に学ぶ――オナモミ(キク科)
ひっつき虫の代表/バイオミメティクス
(2)秋の野に揺れる――エノコログサ(イネ科)
子イヌの尻尾/「C4植物」とは?
(3)秋を象徴する草――ススキ(イネ科)
スクスク伸びる/生きた証「プラント・オパール」
コラム イチョウの学名
第6章 冬の野や庭で、寒さに負けない植物たち
(1)風雪に耐える――タケ(イネ科)とササ(イネ科)
タケが枯れるとき/ネザサの全面開花/タケとササの生きる力
(2)意外なシダ植物――スギナ(トクサ科)
早春に伸びてくるもの/地下茎の恩恵を受ける植物/トクサもシダ植物
(3)日本産のヤシ――シュロ(ヤシ科)
高く高く伸びる/無駄のない植物
コラム 運をもたらす“冬至の七草(種)”
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
モンティ
con
お抹茶
ハラペコ