内容説明
物理学の基本がよくわかる、入門的なまさに科学への入口ともいうべき一冊。
「電子」の発見から、その基本的な性質、量子力学からみた電子のありさまとそのふるまい、あらゆる化学反応の主役ともいうべき電子のはたらき、われわれの生活技術を支える、金属・半導体と電子、そしてヒトをふくむ生物の体の中でも活躍する電子など、世界に充ち満ちている「電子」の性質、その不思議なふるまい、ま支えている支えているその多岐にわたるはたらきを余すところなく解説していきます。
著者は、上智大学で「身近な物理」の講義を受け持ち、科学雑誌ニュートンの監修などでもおなじみの江馬一弘先生。難しいテーマもわかりやすく、面白く伝えてもらいます。
目次
プロローグ 電子はこの世界の主役
第1章 電子は自然界の「最小部品」
第2章 電子の謎の解明が「量子力学」を生んだ
第3章 電子が見せる量子力学的なふるまい
第4章 化学の主役としての電子
第5章 金属と絶縁体、そしてIT社会を支える半導体
第6章 生物の体の中でも電子が大活躍
エピローグ 電子の物理学とその未来
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
haruka
29
ネットもテレビも電力も、現代文明は「電子」を発見し、制御し、活用することで進化してきた。 でもそれどころか身のまわりの現象も、ほぼ電子が引きおこしているよーという内容。 スカスカな原子で作られた私たちが、なぜ床を突きぬけて落ちていかないのか。 植物が緑にみえるのはなぜか。 ATP合成も心の動きも、電子から見たらどうなっているのか・・を探る。 理科が好きでないととても読んでいられない、ちゃんとした本すぎて時間がかかった。 フェルミとボソン、スピンについても少しは把握しておかないと、電子の理解はむずかしい。2025/07/27
kk
28
図書館本。この宇宙の森羅万象全てにおいて電子こそが主役であることを、素粒子論、量子力学、化学、物性物理、さらには生物学などにも触れつつ、一般向けに平易に語ろうとする試み。抽象度が高い数学的な概念などについても敢えて数式を用いず、いろいろなアナロジーなどを用いながら何とか言葉で伝えようとする姿勢がナイス。あとがきによれば、本書の眼目は、読者に完璧に理解してもらうよりも、興味を持ってもらうことの由。その狙いは見事に成功していると思います。2025/08/28
伝奇羊
11
大学時代、高校までやってきた原子核の周りの軌道を電子が回っているという古典的な原子の概念からいきなり打って変わって電子が確率的に存在する電子雲の説明をされて「そんな雲を掴むような話があるか!」とモヤモヤしたのだが本書のように電子の動きで説明されるとよく分かる。本書の物理的な部分は著者の専門でやや難しいが半導体や生物学の話は簡単で以前学んだことを思い出した。よく「観測」によって電子の位置が収束するという話があるが、スリットの実験でよく分かってスッキリした。(シュレディンガーの猫の話も)2025/07/23
こだまやま
11
電子を知れば科学がわかる、というタイトル通り、森羅万象を電子の視点から説明してくれている。化学結合から半導体の仕組み、細胞内のATPの働き、脳内シナプスの話。 重力以外のエネルギーは、電子の動きで説明できると考えていいのだろうか。複雑な世界も究極的に還元すると電子の表現しているものにすぎないと想像すると楽しい。 でも電子とは何なのかというと、例の量子力学の雲を掴む話になり、二重スリットとか観測問題とか哲学のような謎になってしまい、世界はなかなかシンプルに表現できないものよ。2025/07/15
中島直人
6
(図書館)分かりやすく読みやすい。これぞブルーバックス的な本。2025/11/14
-

- 電子書籍
- 大嫌いだった父が認知症になった日 【せ…
-
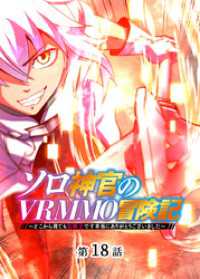
- 電子書籍
- ソロ神官のVRMMO冒険記 ~どこから…
-

- 電子書籍
- 私が親友の彼氏を奪ったワケ【タテヨミ】…
-

- 洋書
- SANG D'ECUME
-

- 電子書籍
- 不倫垢 分冊版 3 ジュールコミックス




