内容説明
司法修習生時代から最高裁の「洗礼」を受けます。
「上」にそれとなく判決の方向性を指示されます。
最高裁に逆らい、見せしめに飛ばされた裁判官もいます。
そのうえ、裁判官が俗物だから、冤罪はなくならないのです。
本書は元判事の著者が「裁判官の独立」がいかに脅かされやすいのか、そして、裁判官がいかに俗物であるかを明らかにします。
袴田事件のようなとんでもない冤罪事件が起きるのはなぜなのか。
その淵源を直視します。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
105
私生活で裁判所のお世話になることがないので興味本位で本書を手にしたが、人事や報酬など下世話な話が多くて、少し残念。尤も「裁判官がいかに俗物であるかをお知らせする」ことが目的とあるから仕方ないか…。ただ、「裁判所の消極性」「裁判官の独立」など、司法の本質に関わることが理解できた気がする。定年まで任期保証される公務員と違い、下級裁判所の裁判官の任期が十年であることを知らなかった。十年毎に最高裁に再任を認められる必要があるから、裁判官の独立の精神を忘れて最高裁の判例を踏襲することに繋がるという実態が納得できる。2025/04/26
skunk_c
64
著者は裁判官を20年やった後に弁護士に転じた人で、著者の知る範囲での裁判官の仕事と日常について、ざっくばらんに書いている。「類書は少ない」と書くが、瀬木氏あたりの著作を読んでいると出ている話も多い。優等生だった司法試験合格者が報酬がそれほど高くない裁判官になった場合、人事権を持つ最高裁判所の方をどうしても見てしまうため、裁判官の独立はこの面で崩れている(長沼ナイキ訴訟地裁裁判長の左遷的転勤はかなり強烈)という主張は首肯できる。その他おもしろい話もあったが、自著の宣伝と趣味の漢詩の話が多い気がする。2025/04/21
あられ
10
裁判官は県境を越えられないの? ←これは知らなかった。海外旅行も許可制なのか。これほど多くの制約を課されつつ、判決を書き続けていらっしゃるのか。そして、勤務地も報酬も、最高裁の思い通り。そりゃヒラメにもなるわいなぁ。。。と改めて思いました。裁判で真実が明らかになる、というのは幻想かも。前例が大事。何事も前例、判例。画期的なことは起こらない。←だいたいのところ。稀に定年退職間近の裁判官が大胆なことをされることがある、こういう方に期待したい。←将来のある方は無難である。。。2025/05/27
スプリント
8
裁判官の仕事や生活上の制約について知らないことが多くよい学びになった。 2025/12/05
おさと
7
結局、私欲のために権力には従わないといけない。サラリーマンだもの。2025/09/24
-

- 電子書籍
- 復讐のシンデレラ【タテ読み】 第8話 …
-
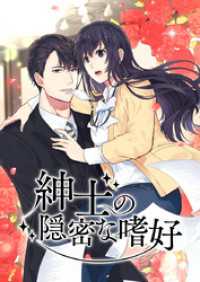
- 電子書籍
- 1話【タテヨミ】
-
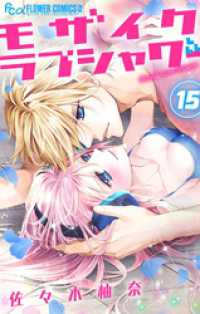
- 電子書籍
- モザイクラブシャワー【マイクロ】(15…
-

- 電子書籍
- ホスグルイ~1億貢いだ女~【分冊版】5
-
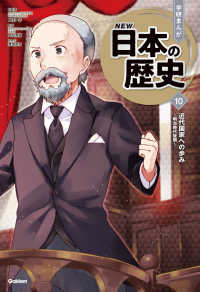
- 電子書籍
- 近代国家への歩み - ~明治時代後期~




