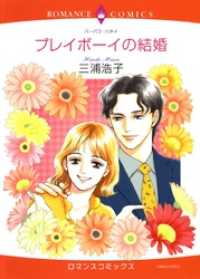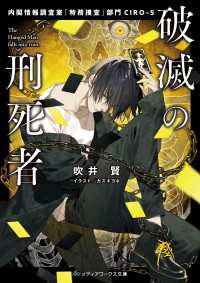内容説明
いままでにない、湿原のすべてがわかる本! 湿原は多くの生き物を育むだけでなく、未来の地球環境をも左右しうる重要な機能を備えた水と炭素の貯蔵源です。他の場所では生きづらい動植物を育み、保水機能によって洪水被害を軽減し、膨大な炭素を泥炭として抱え込んで人間の生活と地球環境を支えている湿原。そんな湿原について、その形成過程から動植物相、直面している問題、そして保全・復元の展望までを楽しく解説しました。
目次
序章 人間と湿原の歴史
湿原と友達になろう
ところ変われば湿原も変わる──水たまりだって湿原
湿原の範囲を決めておこう
湿原は水を抜きには語れない
冷温帯の湿原は泥炭を抜きには語れない
湿原の植物
湿原が地域と世界のあり方を決める
誰がために泥炭は消える
誰がために湿原を保全・復元するのか
〈コラム1〉湿原研究のきっかけ
第1章 湿原の生態系と景観
ヨシスゲ湿原
ミズゴケ湿
同情するなら水をくれ
地形学・地理学での湿原分類
統一見解はなくても湿原は存在する
湿原生態系と湿原景観
湿原は里山景観の必須アイテム
北海道に里山はあるのか
北海道的里山
アイヌ的里山
〈コラム2〉セントへレンズ山の湿原
第2章 湿原の機能──行きつく先は地球温暖化
湿原の物理的・化学的・生物学的機能
生態系サービス──モネの「睡蓮の池」
冷温帯に泥炭湿原は多い
湿原の泥炭は炭素の膨大な貯蔵源
生産力を知ることは炭素固定量を知ること
残された湿原
熱帯泥炭
地球温暖化を加速する正のフィードバック
湿原とメタンとCO2
〈コラム3〉シベリア・アラスカのツンドラ調査
第3章 湿原の遷移
遷移
極相──森林化とミズゴケ湿原化
攪乱──泥炭採掘地を例に
地下部探検隊
日本は火山大国──湿原にも影響するのか
永久凍土と湿原
タイガもツンドラもミズゴケが大事──森林火災とツンドラ火災
森林火災後の遷移
〈コラム4〉野外調査では何があっても動じない
第4章 湿原の保全
湿原保全に必要なツール──生活史を知ること
種子散布──植物が長距離移動できるのは種子の時だけ
埋土種子
成長・死亡
開花結実
タイガ・ツンドラ・泥炭地
〈コラム5〉西オーストラリアにて
種間競争と定着促進効果
食物網
鍵種と傘種
第5章 湿原の復元
「保全から復元」への考え方を確認
攪乱維持型の湿性植生
湿原の乾燥化──湿原の保全・復元の始まり
生物多様性
緩衝帯(バッファーゾーン)
回廊(コリドー)
地形的多様性──谷地坊主って何?
押し出し効果──絶滅危惧種の保全
復元の実践
〈コラム6〉ある調査中の出来事
第6章 日本の湿原(サロベツ湿原泥炭採掘跡地)
サロベツ湿原とは
サロベツ湿原の歴史
復元成果の評価
サロベツ泥炭採掘跡地の遷移
サロベツでもここまでは行けるかも
動物も菌類も遷移する
攪乱と中規模攪乱仮説
〈コラム7〉日本(北海道)の湿原
第7章 湿原の過去・現在・未来
冷温帯域湿原における復元実験
保全・復元の評価ができないと未来はつくれない
スケール依存性要因
自然との共存・共生
再生可能エネルギー(再エネ)との両立
自然再生の最終兵器──ビオトープ
持続可能性と湿原
環境教育(湿原の未来を見守るために)
〈コラム8〉湿原の過去・現在・未来
終章 湿原の豊かさを守る
生態学の応用だけでは保全・復元はできない
環境科学・地球環境科学の必要性
江戸の環境科学
SDGsと湿原
湿原再生の市民科学
SDGsを超えて(ポストSDGs)
最後の最後に──湿原オンリーも困るが
〈コラム9〉再生可能エネルギーと環境保全の両立
おわりに
参考文献
曲名索引
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ろべると
スプリント
Go Extreme
エデン