内容説明
2つの共産主義国家、その歴史を描く
20世紀の世界史を知る上で、また、日本近代史を知る上でも、最も重要な二国間関係の一つである中ソ関係。本書は中国を代表する国際関係史の専門家が、豊富な資料をもとに、下巻では、中ソの決定的な対立から、ベトナム戦争、珍宝島事件、米中国交正常化、改革開放、そして中ソの関係正常化までを描く。
★高原明生氏(東京大学名誉教授・東京女子大学特別客員教授)推薦
『中ソ関係史』は、政権に都合よく書かれた歴史の「常識」を覆し、読者を驚かせる内容を満載している。――(中略)――また、内容は濃密だが訳文はこなれており読みやすい。現在、中露関係は再び大きく注目されている。これは間違いなく、広く読まれるべき本である。
【主要目次】
Ⅲ 分裂から対抗へ(1960~1978)
第16章 中ソ対立の公開と一次的な緩和
第17章 両党関係の破局と両国関係の悪化
第18章 中ソ同盟関係の完全な崩壊
第19章 国際共産運動の分裂と中ソ対立の動き
Ⅳ 「正常化」に向かって(1979~1991)
第20章 「正常化」問題の発端
第21章 「正常化」のプロセスを開く
第22章 「正常化」への転換
第23章 中ソ関係正常化の実現
訳者あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
16
このタイトルで編者:沈志華、訳者:熊倉潤とくると、それだけでもう涎が出そうになる(笑)。中ソの関係を改めて振り返ると、社会主義陣営内部での党間関係と国家関係の融合、国益と陣営の利益と国際共産主義運動の共通の利益の矛盾などから、両国関係には国益の衝突要因が孕んでいたことが当時の時代背景からも見えてくる。細かい点で注目したのは60年代の新疆でのソ連僑民のソ連への帰国を煽った伊塔事件の顛末。この当時の両国の国境近辺をめぐる思惑は極めて興味深いものがある。2025/06/03
Ohe Hiroyuki
3
後半は、中ソ両国が、共産運動路線について大っぴらに対立し、珍宝島での武力衝突をはじめ紛争状態になる等関係が一旦崩壊するところからはじまる。▼中ソ関係の改善にあたって、路線闘争は棚上げし、国家としての安全保障関係等実利を模索していくという変化が起きたことは印象的である。▼上下巻を通して読むと、中ソは、同じく共産運動であったものが、後半は共産とは名が付くものの、国家として別個の動きをしていったことがよく分かる。ここにアメリカが登場するわけだが、本書は複雑な国際情勢の理解を助ける一助となる。大変有益な本である。2025/06/09
-
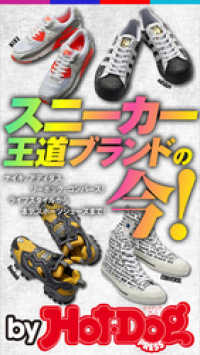
- 電子書籍
- バイホットドッグプレス スニーカー王道…
-
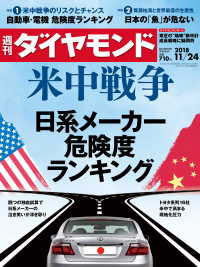
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 18年11月24日号…
-
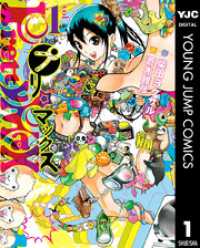
- 電子書籍
- プリマックス 1 ヤングジャンプコミッ…
-
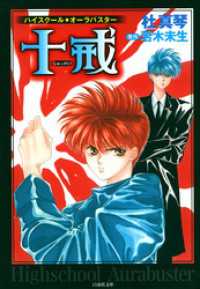
- 電子書籍
- ハイスクール・オーラバスター 十戒 白…





