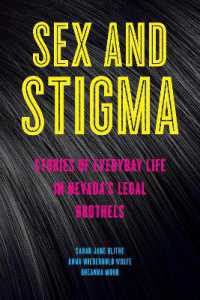内容説明
グルメサイトや地図アプリの検索結果をなぞるだけの日常で生は満たされるのか。情報に覆われた現代社会に疑問を抱いた著者は、文明の衣を脱ぎ捨て大地と向き合うために、地図を持たずに日高の山に挑む。だが、百戦錬磨の探検家を待ち受けていたのは、想像を超える恐るべき混沌だった。前代未聞の冒険登山ノンフィクション。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サンダーバード@永遠の若者協会・怪鳥
101
(2025-13)【図書館本-10】タイトル通り、地図を持たず、四年間にわたり日高山脈を漂泊した記録。角幡氏によると冒険、探検とはシステムからの離脱であるという。システムとはGPSや衛星電話だけでなく、地図も含まれる。なまじ山登りをする身としては、地図も持たず、事前の登山計画も無い登山と言うのはかなり抵抗がある。だが、渓流で魚を釣り、食料を自給しながら、ピークを目指すことなく自由に探索をする山歩きというのも一度やってみたい気もする。でも素人がこれやったら、即遭難だよなぁ。★★★+2025/01/27
アキ
99
「極夜行」と同じく、システムの外側の旅の実験。地図を持たない山登りをすることで、原始の人間と自然との関係を実感できる。その思索の流れが心地よい。地図を持って旅をするということは予測して計画を立てるということであり、「未来予測こそ人間の基本的な存在基盤なのだ」と思い至る。まさに、それは脳の機能そのものではないか。人間の始原的な行為である移動には、必ず地標・ランドマークが必要である。自然の事物に地標を配することで、それが有機的な存在に変わり、自然とのつながりが生まれるのだ。根源的なことを考えさせてくれる良書。2025/01/21
nonpono
89
地図なき旅?地図があっても大山では登山口がわからなく、尾瀬では地図にない道を歩き、雪渓とともに池に落ちそうになった方向音痴な山好きなわたし。「何年もかけて通いこみ、日向という土地をゼロから獲得していく」目標を挙げた著者。沢を登り、魚を釣り、山に登り、キノコを食べる。何百万円もだせばエベレストが団体ツアー登山で登れちゃう今、逆に新鮮で楽しかった。地図を使わないから自ら、地図を作っていく楽しさがそこにあると思う。いろんな冒険を重ねた著者の経験がところどころに生きているんだ。素晴らしい。あー、山に登りたくなる。2025/02/12
R
77
表題から遭難記録かと思ったら、自発的に地図を持たず山へ入るという真の冒険を目指すという、一種の哲学的な実践の記録だった。非常に面白そうだし、共感できるところも多いのだけど、文章に気持ちが入りすぎていて、その熱量と思ったことを書き記しておきたい焦りみたいなのが読めて、温度の高い手記として面白かった。読んでいると冒険の面白さの神髄みたいなのも理解できてくるが、基本的に自儘なので同行者の気持ちもちょっと聞いてみたいとか思ってしまった。楽しそうではあるが、みんなが真似したらよくないことだな。2025/03/05
猿吉君
67
角幡先生がずっと追い求めている冒険の形を実践した作品、ファンなら楽しめるかな。①地図無しで日高山脈を放浪する、のですが日本の中にはもはや秘境は無く、ダムや林道や他のアウトドアマンと会ってしまう。ややこじんまりとした冒険になっているのが残念。②登山というよりも釣りを主体としたアウトドア生活メイン、私は楽しめました。③40代で2週間以上も放浪、リーマンには出来ないので憧れます。点数80/100→初期の作品や極夜行には及びませんが楽しめました、黒い燻製食べたいです!2025/08/24
-

- DVD
- 砂の器 DVDBOX