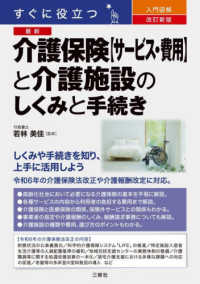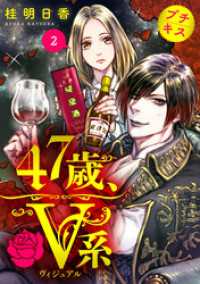内容説明
乳幼児は驚異的な「学ぶ力」で言語を習得できる.しかし学校では多くの子どもたちが学力不振に陥り,学ぶ意欲を失ってしまう.なぜ子どもたちはもともと持っている「学ぶ力」を,学校で発揮できないのか.「生きた知識」を身につけるにはどうしたらよいのか.躓きの原因を認知科学が明らかにして,回復への希望をひらく.
目次
はじめに
第Ⅰ部 算数ができない,読解ができないという現状から
第1章 小学生と中学生は算数文章題をどう解いているか
1 算数文章題につまずく小学生
2 小学生の算数文章題につまずく中学生
3「意味の不理解」が引き継がれる
第2章 大人たちの誤った認識
1 テストと学力についての誤認識
2 知識についての誤認識
3 スキーマなしでは学習できない
第3章 学びの躓きの原因を診断するためのテスト
1 「たつじんテスト」の開発まで
2 「たつじんテスト」は思考力を測る
3 点数をつけるよりも大事なこと
第Ⅱ部 学力困難の原因を解明する
第4章 数につまずく
1 「数」はモノを数えるためにあるわけではない
2 分数というエイリアン
3 かけ算・割り算の意味がわからない
第5章 読解につまずく
1 「読める」とはどういうことか
2 問題文を理解するための語彙が足りない
3 単位,時間,空間のことばを理解できない
4 行間を埋めるための推論ができない
第6章思考につまずく
1 認知処理の負荷に押しつぶされる
2 状況に応じた視点の変更ができない
3 パーツの統合ができない
4 モニタリングと修正ができない
第Ⅲ部 学ぶ力と意欲の回復への道筋
第7章学校で育てなければならない力――記号接地と学ぶ意欲
1 生成AIと記号接地
2 子どもはどのように記号接地しているのだろうか?
3 アブダクション推論とブートストラッピング
4 自走できる学び手へ
第8章 記号接地を助けるプレイフル・ラーニング
1 プレイフル・ラーニングの考え方
2 時間概念の記号接地――プレイフル・ラーニングの実践1
3 分数概念の記号接地――プレイフル・ラーニングの実践2
4 知識を身体化できるのは学び手のみ
終章 生成AIの時代の子どもの学びと教育
参考文献
図版出典一覧
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
tamami
南北
どんぐり
本詠み人