内容説明
グローバル化と国際化が進む現代社会において、バイリンガリズムは重要性を増している。本書は二言語を使うことによって、注意や意思決定といった認知能力、あるいは脳構造・脳機能にどのような影響があるのかという興味深い疑問について、新生児の言語習得、脳機能イメージングなどの神経心理学的研究を通じ、多くの知見を紹介する。
目次
プロローグ
第一章 バイリンガルのゆりかご
ことばはどこにある?
どうしてこんなことされないといけないの?……二つの言語のつじつまがあわなかったらどうなる?
「あっ、わかった! パパとママはことばが違うんだ」
出生前のバイリンガル経験
人は発音のみで生きるものにあらず。口の動き見て察せよ
言語音のレパートリーを組み立てる
単語は何を意味する?
言語習得には社会的接触が不可欠
言語からその人の社会的背景が分かる
第二章 二つの言語、一つの脳
脳損傷とバイリンガリズム
二つの言語を画像化する
言語機能の脳領域を特定する
コントロール、コントロール、またコントロール
脳内の言語操作
第一言語を喪失するということ
第三章 二つの言語を使うとどうなるか?
言語使用頻度と言語間の干渉
心的辞書
バイリンガリズムは、さらなる言語習得の跳躍台になる
自己中心性と「他者」視点
バイリンガリズム対モノリンガリズム
構造的変化
第四章 バイリンガリズムは頭の体操
干渉を避ける
マルチタスキング、または、こちらからあちらへジャンプすると
ああ、残念、全然簡単じゃない!
脳を形作る
さあ、爆弾発表だ─認知機能劣化とバイリンガリズム
第五章 意思決定
コミュニケーション上の文脈がすべてだ
言語と感情、あるいはことばで言い表したいことが表せないとき
意思決定─直感と理性
どの言語を使うか気をつけろ─それによって意思決定が左右されるかも
五人を救うために一人を犠牲にしますか?
社会的マーカーとしての外国語
訳者あとがき
図出典
読書案内
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
三色かじ香
Go Extreme
-
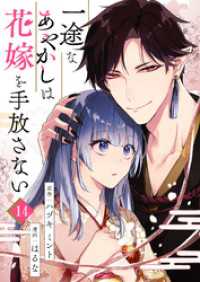
- 電子書籍
- 一途なあやかしは花嫁を手放さない 第1…
-
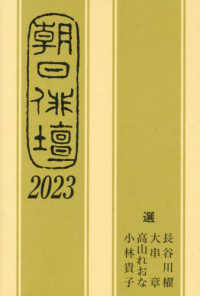
- 和書
- 朝日俳壇 〈2023〉




![逆転の女王<完全版>コンパクトDVD-BOX1[期間限定スペシャルプライス版]](../images/goods/ar/web/vimgdata/4988013/4988013564787.jpg)


