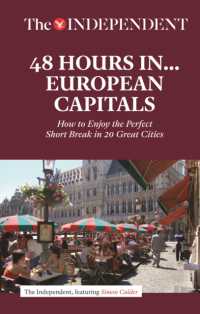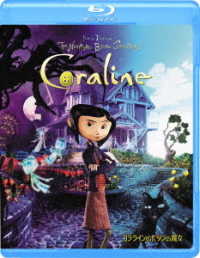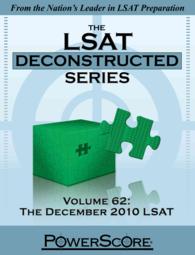内容説明
なぜ日本人は、気候変動問題に対する関心が低いのか。そのヒントは司馬遼太郎や村上春樹らの小説、さらに『鬼滅の刃』『虹色のトロツキー』『満州アヘンスクワッド』などの漫画作品にあった。「未来を変えること」と「過去を新たに見出すこと」は別のものではない。両者は同じ対象を二つの側面から眺めたのであり、その視線は緊密に結びついている。哲学から現代思想、文学、サブカルチャーにまで精通する著者が、日本人が切り捨ててきた<我々の死者〉、そして〈未来の他者〉をキーワードに、過去・未来と現在との「分断」の正体を暴く。
目次
第1章 〈死者〉を欠いた国民
第2章 トカトントンは鳴り響く
第3章 二段階の哀悼――その意義と限界
第4章 仮象としての大衆
第5章 青みどろだけがいた
第6章 スロウ・ボートは中国に着いたか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
41
著者は社会学者だが、本書は文芸批評であり、その上での社会批評だ。文芸批評はエビデンスがないと言われ、説得力に欠けるというのが、読まれていない理由だと思う。著者は以前から加藤典洋『敗戦後論』の仕事を評価している。加藤の論は複雑で、論理を文学の力で乗り越えるところがあった。著者はこれを整理して、日本の戦争の死者たちに対して、あなたたちを裏切ることになると哀悼を示し、次いでアジアの犠牲者に対して謝罪するという、加藤が直接言っていない論として更新した。ではなぜこれが現在の我々に関係があるのか。日本が世界の問題に対2024/05/15
特盛
22
評価2.9/5。日本人が環境問題へ関心が無かったり、世界の人々みたいにデモをしないのは、「我々の死者」を持たず、「未来の他者」を持てないからだ、と著者は言う。戦後の加藤典洋の敗戦後論、鬼滅の刃や村上春樹や太宰など、幅広い思想・文芸批評が関連してなされる。過去の死者ー未来の他人ーアクション、という接続の必然性の宣言がずっと「なんで?」と引っかる。何故それがそこまで確からしく言えるのか?その後、いかに死者を持っていないか、という論証含め後段が頭にあまり入ってこなかった。文芸批評という点では面白いが・・・2024/07/17
nbhd
20
ざっくりいえば、加藤典洋さんの「敗戦後論」が提起した問題を、できるだけわかりやすく解説したうえで、その問題は、村上春樹さんの「ねじまき鳥クロニクル」に内包された文学的論理によって解決できるんじゃね?といった内容の本。大澤真幸さんのウルトラCな思考展開&奇妙かつ強烈なロジックの連続爆撃は、むしろ人文エンタメの領域にあり、途中読み飽きることがなかった。物理学の「量子重ね合わせ」を人文の論理に持ち込む当たりの勢いがマジすごかったわ。内容の好き嫌いは人それぞれだけど、加藤典洋論、「敗戦後論」論として素晴らしかった2024/07/05
marco
14
世界において日本人は気候変動問題に相対的に無関心であるのはなぜか? それは「未来の他者」への眼差しが不足している、とも言い換えることができるが、それはなぜなのか? それは、過去から現在において“断絶”があったから──断絶とはつまりは第二次世界大戦の敗戦であり、過去と現在の架橋に挑んだ作家として、司馬遼太郎、村上春樹の作品を取り上げ推論を重ねていく。本書は、「失ったもの」を取り戻そうとする大澤真幸の挑戦の書である。2025/06/12
エジー@中小企業診断士
12
なぜ日本人は気候変動問題に無関心なのか。それは<未来の他者>への配慮を欠いているからだ。著者はその原因を太平洋戦争における総力戦の敗北によって<我々の死者>を失っていることに求めている。現代の日本人は<我々の死者>の回復と棄却の二律背反の前に立たされている。戦前・戦後の断絶を著者は「鬼滅の刃」の時代設定がなぜ大正っぽいのかを考察することで読者にこれらの問いを前景化させる。太宰治の短編を通じた事前の視点/事後の視点の考察、デリダを導入して日本人の戦争責任に関する哀悼・謝罪の二段階性、最後は村上春樹を考察する2025/08/10
-
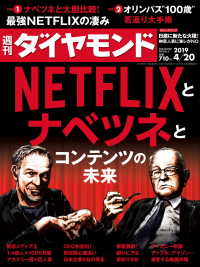
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 19年4月20日号 …