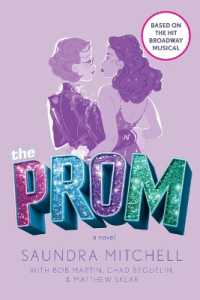内容説明
ヒトの思考の独自性は、それが根本的に協力的なものである点にある。志向性の共有を伴うあらゆる行為をなす点に決定的な違いがあり、協働採食において他者との相互調整を行っていた初期の進化的ステップこそが現生人類の文化を可能にしたのだ。『心とことばの起源を探る』の続編にして『道徳の自然誌』の対となる姉妹篇、ついに登場!
目次
序 文
第一章 志向性の共有仮説
第二章 個別の志向性
認知の進化
類人猿のように考える
競合のための認知
第三章 志向性の接続
あらたな協働のかたち
あらたな協力的コミュニケーションのかたち
二人称的思考
遠近法性──ここからとそこからの眺め
第四章 集合的志向性
文化の発生
慣習的コミュニケーションの発生
行為者中立的思考
客観性──どこでもないところからの眺め
第五章 協力としてのヒトの思考
ヒト認知の進化をめぐるさまざまな理論
社会性と思考
個体発生の役割
第六章 結 論
訳者あとがき
原注
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
9
他の類人猿と異なる現生人類の心理的特徴は他者の意図を理解する点にあり、この特徴が協働する社会を築く基盤となると考える著者は、現生人類の思考を個人主義的な大型類人猿と比較し、認知表象、推論、自己モニタリングの3要素から解明を試みる。その際本書は、進化の過程で個人主義的大型類人猿から協働的現生人類へ移行するには、中間段階が必要と考え、20万年前に出現する現生人類以前の200万年前に「初期人類」モデルを想定する。ここから環境圧力による食料不足を巡って採食活動に転換し、各人が分担する認知方法が生じたと仮説される。2021/12/28
朝ですよね
4
大型類人猿はとても賢く、因果的な推論はできるし自己の行動をモニタリングすることもできる。ただし、それを拡張しても現生人類の思考力には届かないため、この間に進化の観点から説得力のある仮説が必要だ。トマセロは志向性の共有、特に集団志向性というものが大きな役割を果たしていると主張する。志向性の共有はコミュニケーション相手と共通基盤が無いと成立しないし、集団志向性は知らない第三者との共通基盤が必要となる。人間は生まれたばかりの赤ちゃんでも思った以上に社会的な動物だった。2025/08/16
marukuso
4
ヒトに特異的な「客観的-内省-規範的思考」の起源を再構築する。本書では志向性の共有をキーワードにヒトの思考の表象、推論、自己モニタリングが進化的な視点を含みつつ、どう変遷してきたかせまっていく。他者との協働、協力を生み出し、社会的な課題にどうかかわり、適応してきたかを説明する。2021/10/31
borisbear
3
本書の主題は序文にある通り「ヒトの思考の独自性はどこにあるのか」で、類人猿などの思考と根本的に異なる要因、具体的には人間の言語や社会制度や科学的世界観などを可能にしている要因を論じている。本書によると、最近約20年の研究で、類人猿の思考が今まで一般に思われてきたよりも高度であると分かってきたらしい(デネットがポパー的と呼ぶような脳内試行錯誤能力や、志向的構えと呼ぶような読心能力など)。それを踏まえた上で、人間と他の動物との違いとして「志向性の共有」が決定的であるというのが本書の中心主張である。2021/05/10
舞茸しめじ
2
類人猿やチンパンジーを例にして、人間の発達について考察していく本。チンパンジーを使った実験の例が豊富。 猿と人間の差の一つに「他者と協力するという観点の有無」があるというのは面白かった。後は人間以外の猿には映像的ジェスチャー(蛇のジェスチャーとか)が伝わらない話も面白い。 殆どの文章は「分かってる当然の事をわざわざ凄く丁寧に言語化されている」という感覚が強い。そういう意味では哲学書っぽいかもしれない。 ちゃんと実験例や実例を挙げつつ話は展開されていくので、そういう意味では真面目な本。2025/01/12
-

- 電子書籍
- チームを動かし結果を出す方法! 13歳…