内容説明
万葉の昔からはじまり、江戸時代に花開いた日本人の家飲み。当初健康のため、安眠のために飲まれていた「寝酒」は、灯火の発達とともにゆっくり夜を楽しむ「内呑み」へと変わっていく。飲まれていたのは濁酒や清酒、焼酎とみりんをあわせた「本直し」等。肴は枝豆から刺身、鍋と、現代と変わらぬ多彩さ。しかも、振り売りが発達していた江戸の町では、自分で支度しなくても、家に居ながらにして肴を入手することができた。さらに燗酒を売る振り売りまでいたため、家に熱源がなくても燗酒が楽しめた。驚くほど豊かだった日本人の家飲みの歴史を繙く。
目次
はじめに/序章 酒は百薬の長/一 寝酒を飲んで快眠の世界に/二 節度をもって飲めば酒は百薬の長/第一章 万葉集に詠まれた独り酒/一 酒は神と共に飲むもの/二 万葉歌人・大伴旅人の独り酒/三 「貧窮問答の歌」の糟湯酒/第二章 中世の独り酒/一 独り飲みを禁じた北条重時/二 家飲みを好んだ兼好法師/第三章 晩酌のはじまり/一 農民の間にも晩酌が広まる/二 寝酒といっていた江戸の晩酌/三 寝酒のメリットを説く人が出現/四 寝酒の否定論者も出現/第四章 明かりの灯る生活/一 新たな灯火原料の利用/(一)生活時間に夜が加わる/(二)ナタネ油・綿実油・訒燭の利用/二 ナタネ油の生産/(一)ナタネの栽培/(二)ナタネ油の生産/(三)生産量の増加/三 綿実油の生産/(一)綿の栽培/(二)綿実油の生産と普及/四 高価な種油と安価な魚油の生産/(一)高価な種油/(二)魚油の生産と原料/(三)魚油の増産と安価な魚油/五 訒燭の生産/(一)訒燭は贅沢品/(二)訒燭の流れ買い/六 町を巡っていた油売り/第五章 灯火のもとでの外食/一 煮売茶屋の夜間営業/(一)夜間営業の食べ物商売が現われる/(二)煮売茶屋の繁昌/二 料理茶屋の繁昌/(一)料理茶屋が現われる/(二)浮世絵に描かれた料理茶屋/(三)料理茶屋の賑わい/(四)料理茶屋のランク付け/三 居酒屋の繁昌/(一)居酒屋が現われる/(二)深夜営業の居酒屋も出現/(三)居酒屋での独り飲み風景(その一)/(四)居酒屋での独り飲み風景(その二)/(五)江戸には多くの酒を飲める店/第六章 江戸庶民の夜間の暮らし/一 暗かった夜間の生活/(一)夜遅くまで出歩かなかった江戸市民/(二)暗かった家の中の明かり/二 木戸で閉ざされた江戸の町/(一)町木戸の設置がはじまる/(二)徹底されなかった町木戸制度/(三)木戸の閉門はシーズン限定に/(四)潜り戸からフリーパスの木戸/(五)長屋の路地口にも木戸/(六)木戸によって制約された夜間の行動/(七)夜の十時頃には眠りについた江戸の人/第七章 江戸で花開いた晩酌文化/一 俳諧・狂歌に詠まれ始めた寝酒/(一)寝酒を詠んだ句が現われる/(二)雪月花を愛でて寝酒/二 独酌の風情を愛した芭蕉と其角/(一)独酌の感慨を愛した芭蕉/(二)月下独酌の風情を愛でた其角/三 一日の労をいやす寝酒/(一)寝酒が気休めの独り暮らし/(二)町を巡っていた夜鰺売り/第八章 晩酌の習慣が広まる/一 市中に酒が出回る/(一)大都市に発展した江戸/(二)いつでも酒が買えた江戸/(三)二日酔が常習の山崎北華/(四)晩酌は三盃と決めていた太宰春台/二 小咄にみる晩酌/(一)禁酒の誓いを破って晩酌/(二)髪の毛を売って亭主の晩酌代を工面/三 夫婦仲睦まじく小鍋立/(一)三味線を弾きながら小鍋立/(二)舂米屋夫婦の小鍋立/(三)娘の縁談を話題に小鍋立/(四)小鍋立の流行/(五)仕掛人梅安と小鍋立/四 晩酌に飲んでいたのは燗酒/(一)燗酒を飲んでいた夫婦の晩酌/(二)シーズン限定で燗をしていた酒/(三)酒の燗はオールシーズンに/五 なぜ江戸時代の人は燗酒を好んだか/(一)冷や酒は健康を損ねる/(二)超辛口だった江戸の酒/(三)燗酒の習慣から生まれた小咄/六 風呂上りに晩酌/(一)江戸っ子と銭湯/(二)江戸の銭湯の数/(三)銭湯の営業時間と定休日/(四)風呂上りに一杯/(五)湯上り姿の女房を肴に一杯/(六)女性も風呂上りに一杯/七 さまざまな家飲みスタイル/(一)水割りの酒で独り飲み/(二)贅沢な独り飲み/(三)あり合わせの肴で独り飲み/(四)魚売りの魚を値切って内 み/八 孝行息子のおかげで晩酌/(一)養老の滝伝説/(二)養老の滝伝説の影響/(三)豆腐商いで両親の晩酌代を工面/(四)その日稼ぎで両親の晩酌代を工面/(五)野菜売りで父親の晩酌代を工面/(六)野菜売りの一日の収支/(七)大工をして父親の晩酌代を工面/(八)大工の年間収支/九 孝行娘のおかげで晩酌/(一)父親の晩酌の肴を手作りする娘/(二)晩酌の用意をして父親の帰りを待つ娘/(三)火口売りをして父親の酒を買う娘/十 女性の晩酌/(一)老後の晩酌を愉しむ女性/(二)孝行息子のおかげで母親が晩酌/(三)大店のおかみさんの晩酌/(四)漢学者の妻の独盃/(五)やけ酒を飲む女性/第九章 多彩な晩酌の肴/一 肴の名の出現と多様化/(一)肴は酒菜に由来/(二)肴の名の多様化/(三)肴を表わす上方ことば/(四)江戸の肴の呼び名/二 手づくり肴を味わう/(一)多彩な手作り肴/(二)多彩な「なめもの」の種類/(三)惣菜番付にみる酒の肴/(四)手作り肴の特色/三 振り売りから肴を買う/(一)町を巡っていた振り売り/(二)鮮魚売り/(三)夕鰺売り/(四)鰺の食べ方/(五)鳥貝・ふかの刺身売り/(六)枝豆売り/四 屋台店から肴をテイクアウト/(一)食べ物屋台店の繁昌/(二)ワンコイン屋台店の四文屋/五 煮染屋などから肴をテイクアウト/(一)煮染屋に並ぶ酒の肴/(二)味つけの東西比較/(三)大坂で好まれた鼈と鱧/六 刺身屋から肴をテイクアウト/(一)刺身屋には鰹や鮪の刺身/(二)多彩な刺身の調味料/七 仕出し料理のデリバリー/(一)料理茶屋からの仕出し/(二)仕出し屋からの仕出し/八 おでん燗酒売り/(一)蒟蒻のおでん売り/(二)おでん燗酒売りの繁昌/(三)煮込みおでんの誕生/(四)煮込みおでんの普及/第十章 長くなった夜の生活時間/一 木戸の廃止と明かりの進化/(一)明治の町政改革による木戸の廃止/(二)石油ランプの出現/(三)東京の夜を明るくした石油ランプ/二 晩酌という言葉が広まる/(一)国語辞典に晩酌の語/(二)晩酌をテーマにした小説の出現/三 漱石の作品にみる晩酌/(一)『吾輩は猫である』にみる晩酌/(二)『創作家の態度』にみる晩酌/(三)『門』にみる晩酌/(四)『行人』にみる晩酌/四 育まれてきた晩酌文化/(一)晩酌を愉しんだ江戸っ子/(二)電灯の灯る夜の生活/(三)江戸時代に花開いた晩酌文化/おわりに/参考史料・文献一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
グラコロ
ジュンジュン
いとう・しんご
pushuca
-

- 電子書籍
- Sea you! ~凍結スキルで最強の…
-

- 電子書籍
- 【単話】一二三四キョンシーちゃん 第4…
-
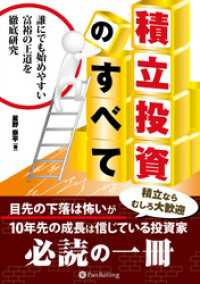
- 電子書籍
- 積立投資のすべて ──誰にでも始めやす…
-
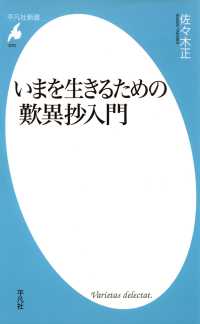
- 電子書籍
- いまを生きるための歎異抄入門 平凡社新書
-

- 電子書籍
- プロフェッショナル 仕事の流儀 秋山咲…




