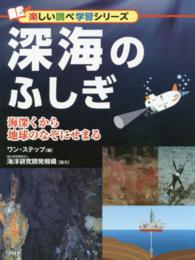内容説明
過去1000年間、技術革新は労働者にほとんど恩恵をもたらさず、ごく一部の資本家や権力者だけを豊かにする傾向にあった。そして現在、AI技術の急速な進展があらゆる職域に自動化の波をもたらし、雇用の崩壊が叫ばれている。歴史の悲劇が、ここでも繰り返されるのだろうか? だが、常にそうだったわけではない。第二次世界大戦後の数十年間、アメリカをはじめとする工業国は目覚ましい経済成長を遂げ、教育と医療の普及、平均寿命の延伸、労働環境の改善などの厚生は多くの人々に共有されていた。両者を分ける条件とはなにか。テクノロジーの進む方向性を転換させ、社会全体の広範な繁栄を実現するための方策とは。当代随一の経済学者アセモグルがMITでの共同研究の成果を注ぎ込んだ決定的著作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
99
技術革新が不平等を拡大させてきたことの後半です。今までにはない分析で今後のこともかなり実現するような感じで書かれています。特に「人工闘争」「「民主主義の崩壊」「テクノロジーの方向転換」で書かれていることは現実に現在起きているような感じです。最後のほうにはいくつかの解決的な方策が述べられていると思われますが、現実にできるような国はあるのか疑問です。いい本でした。2025/12/18
あらたん
67
テクノロジーの進展による利益はときの権力者に集まる傾向にあるけれど、社会制度や政治の努力によってはそれを変えられることができる。 現在のAI革命はそこそこの自動化と民衆の監視に使われていて、全員の利益にはなっていない。 労働者も含めて社会全体に利益が行き渡るよう政策を変えていかないといけない 理解したのはこんなところ。全体としてピケティやハラリを思い出しながら読んだ。2025/06/29
うえぽん
44
ノーベル経済学賞受賞者らが、製粉機、運河、繊維工場、綿繰り機等の歴史上の技術革新は、意図的努力なしには大半の農民、奴隷、工場労働者等に恩恵がなかったことを理由に、デジタル・AI技術が不平等を拡大させない政策の必要性を説いた労作。セルフレジ等の生産性を大して高めないオートメーションや現代版パノプティコンと言える配送センター等ではなく、人間の能力や意思決定を補完するために技術を使うべきとする。その処方箋としての税制改革や研修、巨大テックの解体、デジタル広告税等の適否はさておき、人間中心の技術論は傾聴に値する。2025/12/12
姉勤
38
科学技術が進むほど、大多数の人類は損耗し格差は拡大する。下巻は主に戦中戦後のアメリカの大量生産による社会の変質と、人間の低価値化の推移を。上巻から10章を費やして綴ってきたが、著者が変わったのかと思うほど、最終章でお花畑な理想論が展開する。日本ほか、高度成長期の富の分配と技術発展の相乗を成功例のサンプルとして取り上げているが、現在の我が国の腐敗具合を見ても、不可逆な二重国家化の未来が見えてくる。情報支配からの思考の支配を可能にする従来のメディアと桁違いなAIとネットワークを人類は手に入れつつある。2025/05/31
塩崎ツトム
27
「東京都同情塔」でも書かれていたことだけど、社会的成功者の「わたしは未来が見える・わかる」っていうのは自分の理想を社会に押し付けるだけの政治的権力を持っているというだけで、そういう社会を牽引させる人間にだけテックの恩恵を受けさせると、結果的に大多数の庶民は搾取されるだけというのは上巻でも書いた通り。そしてAI技術はそういう経営者の大言壮語とは裏腹にぼくらの生活を良くはしてくれない。もうボトムアップ式・民主主義式に「この道以外にもある」と、社会の進む方向を変えないといけない。2024/02/29
-

- 電子書籍
- 一郎くんの写真 - 日章旗の持ち主をさ…
-
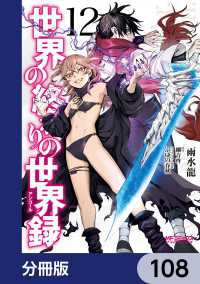
- 電子書籍
- 世界の終わりの世界録【分冊版】 108…
-

- 電子書籍
- だって望まれない番ですから【ノベル分冊…
-
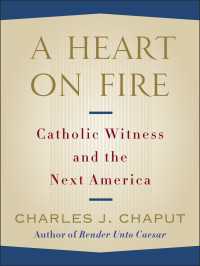
- 洋書電子書籍
- A Heart on Fire : C…