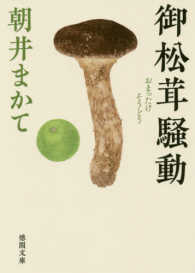内容説明
江戸期以前、女性が一人で旅することは難しかった。身の危険、歩きという制約、何より、男に付き従う姿こそ美徳とされたからだろう。だが、明治維新による文明開化以降、女性たちの旅は少しずつ広まっていく。本書は、日記、手記、聞き書きなどの記録から、全国漂泊、京都への出奔、遊説、米国留学、富士山越冬、蒙古行などの足取りを再現。男尊女卑の風潮が強いなか、時代に立ち向かった女性たちの人生を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
33
11人の旅・移動、あるいは人生のダイジェスト。著者も自認するとおりこれは水先案内の役割。一次資料にあたってみたくなる(例えば岸田俊子や津田梅子)。◉旅の苦労か、生きること自体の困難さか。そこは特に区別されず、季刊誌連載の企画モノなので仕方がないにせよ、少し散漫な印象。逆に言えば、深掘りして欲しい切り口は沢山含まれている。◉歴史に埋もれてしまった「女の旅」は無数にあるのだろうな。在日外国人労働者の母語によるつぶやきとか、壮年になったかつての留学生たちの青春記とかに興味が広がりました。2019/09/01
佐島楓
20
考えてみればこの本を読むまでは渡米後の津田梅子の苦労まで知らなかったのだなあと改めて思う。航空路がない時代、皆女性は偏見と闘いながらもものすごい苦労をして見聞を広めていた。私も挑む気持ち、変化を恐れぬ心を持ちたいと願う。こういう切り口の歴史物は好きです。2012/05/20
奏市
14
古本屋で目につきなんとなく買ってみたが、面白かった。幕末から明治期に旅に出た11人の女性の短い伝記。教科書的な歴史記述でない人々の暮らしや女性の立場などが垣間見えて勉強になった。留学、遊説、俳句、夫への随伴等色々な理由で旅に出る。ヨーロッパへ渡り芝居が人気となった花子。たまたま直前に読了したドナルド・キーンさんの『日本人の美意識』で評論あり知ったばかりの人物だったので、偶然感楽しんだ。ロダンが彼女を気に入り顔の彫像複数作ったと。夫の富士頂上での気候観測に当人から危険だと反対されても付添った野中千代子凄い。2021/07/03
きいち
9
おりょうと津田梅子、番外編のイサベラバード以外は知らなかった人たちばかりでとても興味深かった。関所での足止めすら句のネタにした冒頭の田上菊舎、投獄された岸田俊子への母親からの率直そのものの励まし、この2本が特に好き。仕事だけじゃなく家族や生活が重要な側面の1つとして語られるおかげで、旅と生き方そのものとの関わりがより強く印象付けられる、稀有な本となってると思う。一人ひとりもっと詳しく知りたくなる。2012/07/01
犬養三千代
8
幕末から今までの女一人旅を扱う。従者は含まない。明治維新ごの津田梅子の旅、留学なんだけど辛かったかなぁ?いや、6歳くらいだから日本忘れたんだろうなあと思った。河原操子は知らなかった。モンゴルで教育係だって。どの時代もたまたまその立場になったり自ら立ち向かったりした女子は凄い。2023/01/04
-

- 電子書籍
- 愛されてる場合じゃないの 40話「一生…
-
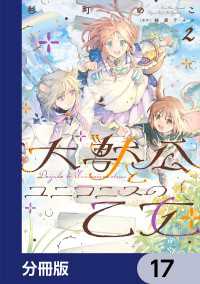
- 電子書籍
- 大獣公とユニコニスの乙女【分冊版】 1…
-
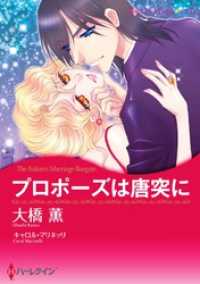
- 電子書籍
- プロポーズは唐突に【分冊】 7巻 ハー…
-
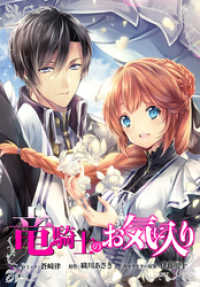
- 電子書籍
- 竜騎士のお気に入り 連載版: 10 Z…